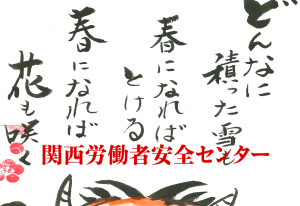事哉と恐怖で「心因反応」認定:労災隠しの親会社に補償と対策要求/神奈川
全造船機械日本鋼管分会
目次
ドック入り
海に浮かぶ大きな船、その水面下の部分の修理はどうやって行うのだろうか。鉄板を切ったり取り付けたりする作業は、当然水中ではできない。そこでドック(堀わり)の中に船を入れる。ドックの中の海水をポンプで外に排水する。そのまま排水し続けると、船は傾き倒れてしまうから、ドヅクの底に、盤木(ばんき)と呼ぶ、いわば大きな積木のような木や鉄を置き、そっと船底が上にのってバランスが保たれるようにする。そうすれば、海水を全部出し、船腹に対して両側のドックの壁からも固定するようにし、作業が開始できるというわけだ。
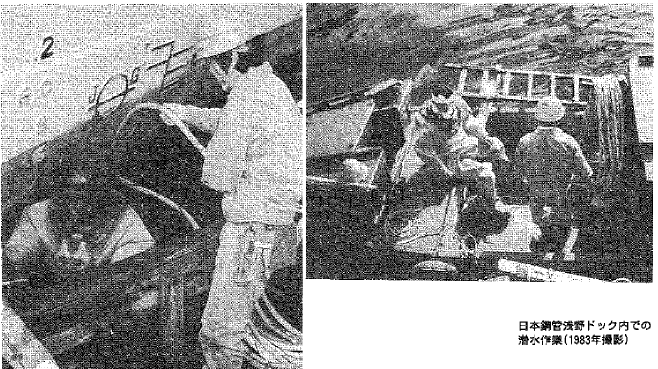
事故発生
日本鋼管の浅野ドックは、東神奈川〔横浜市)にある修繕の専門工場。1989年2月にはインド船の爆発・火災事故で13名が死亡するという大惨事があった工場であり、日本鋼管全体の合理化の中で今年中に閉鎖が強行されようとしている職場でもある。
1990年10月15日、浅野ドックでの盤木の調整作業中に事故が発生した。潜水工歴35年のベテランKさんは、潜水作業中に作業船 (ダイバー船)からの送気ホースが本船にはさまれたのに気づいた。
誤って、日本鋼管のT職制がドックの水を排水するバルブを回したため、本船が沈みだし、盤木の間にあったホースをふさいだのだ。ダイバー船には、Kさんの所属する日本鋼管の下請D産業の社長が乗っている。必死でつながっている電話に救助を求める。しかし、ホースはっぶされたまま。潜水用ヘルメット内に残るわずかな空気。恐怖と苦しさは、次第にもうろうとした気分に変わっていったという。
異常に気づいた社長が、あわててT職制に指示、バルブを操作し、注水。本船がわずかに浮上、つぶされていたポーズから窒息寸前のKさんに空気が送られた。助かった…。もうあと、そう、10秒でも遅れたら、Kさんの命はなかった。潜水具一式の重さは75~80キロ。自力で上るすべはない。
潜水用エアホースで船に引き上げられたKさんは、そのの場にへたりこんだ。怒る気もうせていたという。抜けがらのようになって、その日は電車で自宅に帰った。実は船に引き上げられた後の行動や、どうやって帰ってきたか、Kさんは覚えていない。後日、D社長に教えてもらったのだという。3日間、恐怖にうなされ、食事もとらず、布団に伏したまま。
労災申請だけはしないでくれ
説得にかかるかかる会社
10月19日、自宅近くの横須賀市立市民病院で診察を受ける。
病名は「心因反応」。あまりにも大きい恐肺体験のため、不眠、不安、うなされる閉所恐怖、食欲不振にも苦しめられ、仕事はもちろんのこと、日常生活でも多大な被害を被ることになったのだ。しかも、後に紹介するように、このような事故はKさんにとって2度目。それだけに心の奥深くきざまれた傷は大きかったのだ。事故による両方の耳の感音難聴、耳鳴りもるうつらかった。
幸いなことに主治医は「これは業務上の事故。あとで後遺症が出たりしたら困るので、労災にしてもらうように」と言ってくれた。病院の方も労災扱いにしてくれると言う。早速、奥さんが社長に「労災にしてください」と言いにいった。ところが、「金銭的には絶対迷惑をかけないから、労災にだけはしないでくれ」。再度頼むと、10月23日、社長と浅野ドックのN工場良が自宅に来て、「金銭的には絶対迷惑をかけないから、労災にしないでほしい」と繰り返し、帰っていった。その後も、同じことの繰り返し。事実、給料相当分は毎月支払われていた。
1992年7月になり、社長は「これ以上払い続けることはできない」と言う。後でわかったことだが、N工場長も「金銭的に迷惑はかけない」と言ったが、日本鋼管がD産業にKさんの休業中のお金を払ったのは、最初の3か月だけ。その後はD産業が支払っていた。しかも、社長とKさんの2人でやってきたのが、この事故のため、日本鋼管から入ってくるのは1人分の仕事に対するお金。第一、潜水作業は1人ではできない。D産業も廃業せざるを得ないところまで来ていたのだ。
分会に相談一労災申請~認定そして日本鋼管の責任追及へ
思いあぐねたKさん夫妻は、日本鋼管分会に相談。Kさんは浅野の現場で、分会の持橋委員長とは顔見知り。1979年に分会結成とともにユニオンショップ解雇、そして1985年の職場復帰するまでの闘いを、心から応援していたとのこと。
1992年7月31日、分会に加入。D産業に引き続き休業補償を支払わせるとともに、D産業、そして日本鋼管に対し、労災申請の手続をとるように要求。実に発症以来1年近くなってから手続がとられ、さらに、心因反応、うつ病、閉所恐怖症が労災認定されたのが1993年10月、両感音難聴、耳鳴りが認定されたのがその半年後だった。この遅れは、Kさんにとって不安が募るつらい日々だった。その遅れの理由として、横浜北労基署は、「心因反応」の労災認定例が極めて少ないこと(過去に3例)、事故発生後1年もたってからの申請であることをあげた。
分会は日本鋼管に対し、次のような要求をっきっけた。
- 事故の経過と原因を明らかにし、日本鋼管の責任を明確に認めること。
- 今後の安全対策
- 労災隠しに至った経過と今後の対策、責任者の処分
- 謝罪及び明確な補償
事故の真因は?
事故発生後、日本鋼管が作成した事故報告書では、この件を「ヒヤリ事故」、つまり、ヒヤッとしたが労災事故ではなかった、とした上で、「お互いの連絡の不徹底」を原因としている。これからは気をつけましょう、というわけだ。
では、どんな事故であったか。
ダイバー船は、本船のさきに向かって左側(左舷)に位置していた。Kさんは左舷側から潜り、盤木の調整をしながら、右舷側に移動する。その最中に左舷側に気泡が上がってきたのを、Kさんが左舷側に戻ってきたと勘違いしたT職制がD産業の社長からの合図もないのに、排水バルブを操作し排水、そのために本船が沈みはじめホースがはさまれたのである。
前にも同じような事故が
たしかに、T職制が勘違いせずに、バルブを動かさなければ事故は起きなかった。だが、Kさんの話を聞いていくうちに、それ以前にも同じような事故が起きていることを知った。
1976年、同じく浅野ドヅクでの潜水作業中、2号ドックの右舷の第1自動盤木と船底の間にホースがはさまれ、あわや、という事故があった。自動盤木のハンドルの取り扱いのミスだ。この時は、右舷側より潜水、左舷の盤木を確認中だった。担当者が間違って、開閉の表示と反対にハンドルを取り付けていたのだ。助け上げられるなり、Kさんは怒鳴りっけたという。恐怖と怒りで精神的ダメージを受け、1週間休業。D産業からも日本鋼管からも、電話1本よこさないことに怒って、奥さんは、横浜北労基署へ「昨日、浅野ドックでダイバーがもう少しで死にそうな事故にあった。事故報告は来ていますか?」と電話。このため会社は監督署に呼ばれ、注意を受けたという。 奥さんもKさんも、実家は潜水一家。奥さん自身、ダイバー船に乗って、エアホースを握っていたこともあり、このようないい加減な会社のやり方は許せなかったのだ。
共通する間題
この2件の事故に共通しているのは、次の点だ。
- 本船の底をくぐるかたちで作業が行われている。このため、何らかのミスが発生すると、エアホースがつぶされる危険性が高い。
- いずれも作業者の単純なミスとして処理され、「注意して作業する」ことのみが強調されてすまされた。
- 労災隠し。2回とも休業を必要とした事故であるにもかかわらず、労災としての手続を行っていない。交渉で明らかになったことだが、1回目の場合、会社の安全室に事故報告すら届いていない。
- これらの事故があったにもかかわらず、潜水作業についての会社としての安全基準や、緊急時のマニュアルが作られなかった、「潜水作業は下請がやるもの」という認識があったからだろう。
責任を認めた日本鋼管
1992年10月の事故は、むしろ起こるべくして起こり、その後のKさんに対する扱いも、日本鋼管の体質からくるもの、と断じて私たちは会社を攻めた。日本鋼管は責任を認めた。その結果、「ヒヤリ事故報告書」を撤回、あらためて災害報告書を作成しなおした。
また、安全対策として、
- 可能仕事はアクアラングで行う
- アクアラングでできない作業については、エアホースが船底をくぐるかたちになる潜水作業はやらない
- 有線電話をより感度のよいものに
- 調整不要の自動盤木の導入
- 連絡の徹底
などを行うこととした。
2.の改善とは、例えば、船の左舷側の盤木作業の時は、ダイバー船を左舷側にとめ、潜水者は右舷側にまわらない。右舷側の仕事をする時は、ダイバー船ごと右舷側にまわるというやり方。Kさんの兄弟が潜水の仕事をやっている住友の造船所では、以前から、左舷側の作業は左から潜り、右舷側の作業は右から行っている。それが潜水作業の基本である。船底をくぐるやり方の危険性を知るKさんが、しばしば日本鋼管の職制に対し、この方法をとるよう話したが、聞き入れられなかったという経過をもつ。
労災隠しについては、労基署の署内で、N工場長、D産業社長とKさんの奥さん、分会が「対決」。N工場長は、労災にしないという方針は上司である修繕船部の部長の了解の上であったことを認めた。その後の会社との交渉で、「仕事によるケガや病気が労災であるかどうかは、監督署が判断することなので、直ちに監督署に申請手続をとる」ことを確認。
何をいまさら、という内容だが、過去日本鋼管においては、会社が認めたもの以外、一切証明や手続を拒否、分会が取り組み、会社の証明なしで監督署へ持ち込んで認定を受けるというかたちが通常だったから、会社の反省のあらわれとみてよいだろう。
そして、時間はかかったが、1995年2月、謝罪と補償責任を明らかにした確認書の調印をみた。Kさんは現在もなお労災保険で治療、休業を継続中であり、損害額の確定ができない。そこでまず補償責任を明確にし、内金を支払わせ、障害等級が決定した時点で、最終決着を図る内容である(補償責任は全て日本鋼管が行う。D産業とは、退職金の支給というかたちで合意)。
闘いを振り返って
この闘いを振り返ってみると、次のようなことが言える。
- 労災隠しを許さず、主治医の協力もあって、きわめて認定例の少ない「心因反応」を労災として認めさせたこと。
- 事故発生率の高い造船業、しかも協力会(下請)労働者の被災率はさらに高い。その中で親会社の責任を明確にし、補償責任をとらせたこと。本工との差は一切認めないということでもある。
- 事故原因に迫り、「個人の注意」のみに頼る小手先の安全対策ではない抜本策をとらせたこと。
- 労災保険の請求者は被災労働者本人であり、これ以後会社が認めない場合も労災申請の手続をとり、監督署の判断をあおぐようにしたこと。
これらの成果の根本に、Kさん夫妻の負けてたまるかという強い意思があったことは言うまでもない。この言わば、第一次解決がKさんの症状の改善に大いに役立つことを期待したい。
安全センター情報1995年5月号