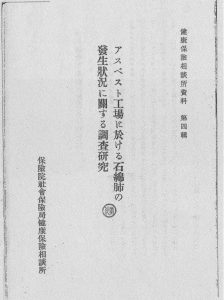隠された泉南アスベスト(石綿)、被害の現場を歩く 五 底知れぬ石綿被害の広がり 柚岡一禎
■石綿被害のまち
2005(平成17)年6月、クボタによる石綿被害が発覚したとき、筆者の正直な気持ちは、「尼崎にも石綿はあったのか?」というものだった。石綿は泉南だけの話と思っていたからである。当時すでに泉南の石綿産業は衰退していて、イシワタ(地元呼称)は日々遠い存在になりつつあった。済んだ話を今更なあ、ぐらいにおもったものだ。
待てよ、泉南には尼崎より大きな被害があるに違いない。そう考えて同年11月、有志で「泉南地域の石綿被害と市民の会」を立ち上げ、潜在的な石綿被害者を掘り起こす活動を始めた。
同年11月27日、泉南市立樽井公民館で行った「泉南地域石綿(アスベスト)被害医療と法律の個別相談会」で、泉南の被害の実態をまざまざと見せつけられることになった。当日は、開始時刻より早く、新聞折り込みを見た100人を超す市民が押しかけ、診察の順番取りにもめ事が起きるほどになった。当地の石綿被害に対する関心の高さを感じた。相談者の中心は50歳代から70歳代の中高齢者であったが、40代の若年層も大勢いた。
彼らは、「石綿被害について、どこに行って話をしたらいいのかわからず困っていた」「体の調子が悪く、不安だった」「とにかく話を聞いて欲しかった」と口々に述べ、不安や疑問を話しただけで安堵して帰っていく人もいた。
この日の相談者数は99名、うち83名がレントゲン撮影を受けた。驚いたことに、83名のうち53名に石綿関連疾患(疑い含む)の所見が認められた。健康被害は、石綿工場で働いていた者だけではなく、近隣住民にも見られた。「地域全体の石綿被害」は数字でも裏付けられた。
「泉州地域の被害、重層的で深刻-このように、泉州地域の石綿被害は、石綿工場の従業員、家族、周辺住民、零細事業主とその家族と、重層的かつ深刻なものになっています。現在は発症していなくても、数十年の潜伏期間を経て多くの被害者が発生する可能性もあります。しかし、効果的な対策も、住民全体を対象にした健康診断も疫学調査も行われないままです。補償についても、ほとんどが中小零細で、しかもほとんどが廃業していることから、事業主の責任能力には疑問があります。労災を申請しようにも、医学的所見が確認できない場合が少なくありません。こうしたことから、市民の会などは政府・行政の責任で問題を解決する必要性がきわめて大きいと強調しています」(2005〔平成17〕年12月14日新聞赤旗)
相談会に来て初めて、自分が石綿の病気であり、手続をすれば毎年無料で健康診断を受けることができ、また労災補償の対象となることが分かったという人が何人もいる。原告の一人は、体をこわし、仕事もできず、労災もなく、生活苦に悩んだ。病院に行こうにも、お金の心配が先に立って長い間ひとり苦しんでいたのだ。後に原告となった前川清、佐藤健一、石川チウ子、原まゆみ、江城正一も、この相談会の後に労災給付を受けられることになった。
不安を持っている人たちは大勢いて、救済を求めている。このことを国に分かってほしいと思った。
■埋もれた被害を掘り起こす
市民の会には今も相談の電話が入る。
昔、石綿工場で働いたので不安だ、近所に石綿工場があったが大丈夫か、工場から白い綿が出ていた、というものから、建設関係の仕事をしていて体調が優れない、家族が石綿工場で働いて肺がんで死んだが補償は?という相談もある。昔、泉南に住んでいた、泉南の石綿工場で働いていたという電話が、北海道や九州から入ることもある。適当な相談先がないのだろう。
市民の会発足以降、数回の医療法律相談会と個別相談を行った。2009(平成21)年7月末現在の相談者は、およそ350名。このうち8割以上は岸和田市以南の在住者である。石綿工場の労働者、労働者家族をはじめ下請、内職、工場の出入り業者、工場近くに居住していた人とさまざまで、昭和初め頃から20年代生まれが多い。高齢になって初めて石綿による被害を知り、相談に来たようだ。このうち、実に40%近くが、石綿関連疾患(石綿肺、びまん性胸膜肥厚、肺がん、中皮腫、胸膜プラーク)の診断を受けている(いずれも疑い含む)。石綿工場の近隣で居住ないし労働していた人で、「風邪をひきやすい」「痰がよく出る」などの症状を訴える人もいる。
本人や家族が健康被害の心配を抱えている場合、市民の会のメンバーが阪南医療生協診療所(岸和田市)での診察に付添うことになる。労災申請や健康管理手帳の交付申請が可能な場合は、そのサポートをする。相談者の状況は、弁護士につないだ後も把握して関係が切れないようにしている。
相談者から、「誰彼と一緒に働いていた」「この人は肺の病気で入院している」「あの人の家族は肺がんで亡くなった」などと聞くと、それを手がかりに聞き取りを始める。しかし、泉南から他地域に転居したり、いくつもの工場を転々としている場合、追跡は難しい。
「あだ名で呼んでいたので本名を知らない」「実家に帰ったらしく今の居場所が分からない」ということも多々あり、最後まで行きつかないことも度々である。
話が聞ける人には何度も会いに行く。石綿工場のあった場所を教えてもらうこともある。
三好石綿に和歌山から通勤していた人や、島根県隠岐から働きに来ていた人たちが相当数いること、泉南市内に第2工場、第3工場、千葉県にも工場があり、そこで働いていた人がいることも、地道な聞き取りを進める中で分かった。2008(平成20)年5月と11月には、弁護団と市民の会、元労働者で隠岐を訪れた。隠岐郡西ノ島町で少なくとも29人の労働者がおり、その内追跡できた7人に何らかの石綿疾患が明らかになっている。
このようにして、これまで市民の会が相談を受けたり、直接あるいは電話で話を聞いた人は600名を超えた。
■ある女工の場合
泉佐野市の相談は切実だった。2006(平成18)年5月、相談会の折り込みビラを見て電話をしてきたのは、74歳の元女工だった。1954(昭和29)年に結婚、夫婦で泉佐野市にあった石綿パッキン製造会社で働いた。4年後、女性は出産のために退職したが、夫は働き続け、1966(昭和41)年32歳で肺がんで死んだ。生前の写真を見ると、若い青年の姿があり、女性の悲しみの深さを思った。
夫は、生前、石綿肺で労災認定を受けていたようだが、死後労基署の職員が自宅を訪れ、肺がんと石綿肺は関係が不明、研究が進んでいないと言われ、労災を打ち切られた。夫の死の2年後、女性はまた同じ石綿工場に戻り、9年間働いた。その結果、咳や息苦しさに悩むこととなった。夫を奪った石綿工場に戻るなんてとんでもない。我々が今こう思うのは、石綿の危険性を十分に知っているからである。
女性は、7歳の子どもを抱え夫に先立たれ、生活は苦しかった。4歳で母を亡くし、小学4年生のとき父親が失明したために学校をやめて働いた。読み書きも満足にできず、親も頼れず夫に先立たれた。困った女性は、「マスクをすれば大丈夫だろう……」という程度の考えで、再び石綿工場に戻った。今になって無知を悔やむが、当時の彼女からすれば、石綿工場で働くしかなかった。彼女の知る唯一の生きる道が石綿だったからだ。
この女性には、夫の死について、石綿新法による補償が出ることとなった。当時の医療や労災の記録はなかったが、女性が大事に残していた夫の入院時の見舞客帳に、「石綿肺 昭和37年12月」という記載があったことが決め手になった。
■差別が覆い隠す石綿被害
戦前筆者の祖父がやっていた「弥栄石綿」の写真に、朝鮮人男女工員7人が写っている。また叔父の出征記念に撮った写真にもチマチョゴリ姿が何人も見られる。昔の栄屋石綿を知る者からも朝鮮人石綿工の話を聞いた。戦後この地で起業した石綿業者に、在日コリアンが多いことは周知の事実である。聞き取りの中で「イシワタ(地元の呼称)は朝鮮人のやる仕事や」といった差別的な発言も何度か耳にした。当然被害者には在日コリアンの比率が高い。
被差別部落住民が石綿工場で働いていたことも聞き取りの中で分かった。泉南市の大手石綿工場のひとつ東邦石綿に、戦前から戦後にかけて、近くの被差別部落から若年労働者が大勢通っていたとの証言がある。また、九州、沖縄、山陰、四国、和歌山からも多くの労働者が職を求めて泉南に来た。
戦前から戦後にかけて、泉南の石綿紡織に関わった人たちの中に在日コリアンや被差別部落、地方出身者、炭鉱離職者が多数いたことが、石綿被害を覆い隠し、見えにくくしたひとつの原因ではないかと考えている。マスコミが取り上げ被害の実態がかなり明らかになった今も、泉南の石綿問題に口を閉ざす人が多いのには、このような背景があるように思う。
誤解を恐れずに言えば、日本社会の底辺で生きる人たちの行き着いた先が泉南の石綿だった。彼らは貧しさゆえに、汚れ仕事も長時間の労働も厭わなかった。経営者は大した資本をかけずに必要なら自分と家族の労力も投入したし、労働者は教育水準や技術訓練を要求されることなしに、働いたその日からそこそこの収入を得ることができた。
ナッパ服を着て行き来する石綿労働者に、地元住民は「無関心」をつづける一方、一種の蔑(さげす)みの目を向けていたように思う。零細な紡績工場に通う者を「こうばいき(工場行き)」と呼んで、一段低位に見ていた。また仕事が嫌いで怠惰なものがいると、「イシワタ工場に放り込むぞ」などと脅したという話も聞いた。当時泉南で、繊維労働者として働いた者たちの立ち位置が分かる。
毎日頭や顔に白い粉じんをつけたまま帰ってくる石綿労働者は、「こうばいき」の典型だった。イシワタの病気のことも日頃聞いて知ってはいるが、所詮は彼ら「こうばいき」の話で我々には関係ない。地元の意識はこの程度であったように思う。行政が石綿被害に鈍感で、市民の会から指摘を受けた今も調査に乗り出すことに消極的なのも、このことと関係があるかもしれない。
だからこそ思うのである。国が対処する必要があったと。70年も前から、工場内外の凄まじい石綿飛散の実態をつかみ、対策の必要を記録に留めていたのは国だった。自らの調査で石綿の人体リスクがただならぬ事を知っていたのも国だった。やろうと思えばできたはずだ。全面禁止に至らずとも、集じん装置や防護服の開発ぐらいは、戦前は戦艦大和の戦後は世界に冠たる精密技術の、ほんの一部をもってすれば容易だったろうに、それもしなかった。
それさえせずに、国は産業政策優先で泉南に石綿を押し付けた。泉南の石綿業100年の歴史は、被害の100年でもあった。
聞き取りを始めて以来、多くの人から話を聞いた。現場をよく知るすでに高齢の彼らは押しなべて言う。あの人も死んだ、この人も死んだ……10人ぐらいの名前はすぐに挙がる。すべてが石綿由来でないにしても、職歴と死に様から限りなくそれをうかがわせる。過去の岸和田労基署の調査は、岸和田労基署管内の石綿労働者の平均寿命が、日本人のそれより男で14歳、女で19歳短いことを報告している。衝撃的ではあるが、実態に沿うものだろう。
泉南地域の石綿被害者は数千人規模であり、我々の見つけ出した被害者は全体のごく一部、いわば「生き残り」であるというのが筆者の実感である。被害者の一人から言われことがある。「今更なんや」「手遅れじゃ」。胸に響く。無力感を覚えつつも被害者救済のために奔走する毎日である。
おわりに
最後に、筆者自身のことを述べて本稿を終えたい。1960年代京都で学生生活をおくった。当時のベトナム反戦運動の盛り上がりは筆者のような者にも平和、人権、自由、平等を深く考えさせたし、それなりに勉強もした。社会に出たら学んだことを活かして、月並みに言えば「世のため人のため」、役立つ人間であることを期した。
それがどうだ。京都を離れ家業の紡績経営についた途端、青臭い理想はどこかに吹っ飛び、以後俗界にまみれた。当時泉南の石綿業は全盛期を越えていたとはいえ、まだ多くの工場は操業を続けていた。当然ながら石綿労働者はおおくいた。先述した「こうば行き」の姿にも日常的に接した。彼ら下層労働者の労働環境をよく知る位置に自分はいたのだ。しかし何もしなかった。
本稿で筆者は、国の無策を糾弾し無知蒙昧な工場主に怒った。しかし真に非難されるべきは、石綿労働者の窮状に目を向けず見過ごした者たち、同情どころかさげすみの感情さえ持った我々地元民ではなかったか。その一角に筆者もいたのだ。
祖父が起した石綿業によって一族は潤った。子供心にも裕福な生活だった。石綿労働者が蒙(こおむ)った苦難に目隠しをして生きてきた。尼崎でクボタ被害が発覚するまでは。そして「あんたの爺さんの工場ではたらいたんよ」という老婆が現れるまでは。そのことを恥じる。
ゆおか・かずよし
1942年5月生まれ。「泉南地域の石綿被害と市民の会」代表。学生時代を除き泉南市に在住。紡績業を経て現在は建築業。 京都大学文学部卒。 武道教室「有朋館」主宰。株主オンブズマン会員。