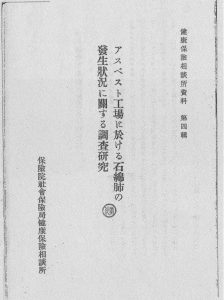隠された泉南アスベスト(石綿)、被害の現場を歩く 三 石綿粉じん-誰も逃れられない 柚岡一禎
■雪のように降り積もった
石綿工場での粉じんの飛散は激甚で、従事者は逃れようがなかった。原告被害者たちの証言をもとに実態を紹介しよう。
1975(昭和50)年頃の三井石綿は、工場の入り口を開けると全体が真っ白だった(佐藤健一)。親和石綿は、石綿の綿と粉じんが粉雪のように飛び散り、前が見えにくいほどだった。機械や床に雪のように降り積もっていた(原田モツ)。
以前の栄屋石綿の工場内は、着ている服、帽子に石綿が積もった(前川清)。昭和40年代の西河石綿の工場内は石綿の粉じんが舞い散り、濃い霧のように煙っていた(岡本郡夫)
「作業が終わると、体、特に口、鼻、首筋など服から出ている部分に石綿のほこりがついて、白くなっていた」「まつげ、眉毛も真っ白になった」(湖山寿啓、原まゆみ、戸口義弘、松島正芳、禰占マス、礒田ゑみ子)。「夏場は、汗でほこりが皮膚にべったりとこびりついた」(岡田春美、古川昭子)。
頭にタオルや三角巾をかぶっていてが、はみだしている部分の髪の毛に石綿のほこりがたまり白くなった(禰占マス)。タオルやマスクで口と鼻をおおっても、口や鼻の中に石綿の粉じんが入って、口の中がじやりじゃりになり、痰も灰色になった。マスクをしても、マスクを通してほこりが入ってきて、鼻をかむと、石綿が混じってねずみ色になった(米山一夫、原まゆみ、松島正芳)。
(作業中マスクを着けると息苦しくて仕事にならなかったと語る者は多い。なぜマスクをしなかったのかと詰問する国側の主張は、石綿工場の作業状況に無知な者の言い草だと、筆者などは思う。)
石綿の粉じんが肌に張り付いて気持ち悪く、ちくちくと痛がゆかった。頭皮にも刺さっているような感じで、洗っても取り切れず、いつも痛がゆい状態だった。粉じんが、服やシャツなどの中まで入ってきた(青木善四郎、藪内昌一)。
トイレに行って作業着のズボンを脱ぐと下着の中まで石綿のほこりが入り込んでいた。三角巾や帽子をかぶっていても頭の中にほこりが入り込んだ(石川チウ子)。
工場の床には、白い石綿の粉が新雪のように積もって、歩くと足跡がくっきりついた(木下お栄)。工場の窓ガラスや天井の梁には、石綿粉じんが5センチメートルくらい積もっていた(簑田努)。
カード機のメンテナンス「針とぎ」(エメル)の作業は、とりわけ粉じん飛散が激しかった。「前が見えないくらいすごい飛散」「床に石綿が積もり、マスクをしていても顔が真っ白になった」(前川清、藪内昌一、戸口義弘、佐藤健一、湖山寿啓、簑田努、松島正芳)。
一日の作業が終わると、機械の下や床に落ちた粉じんを掃除した。ほうきで床を掃くと、積もった粉じんが工場内にもうもうと舞い、嫌でも吸い込んだ(岡田春美、松本玉子、原田モツ、古川昭子、岡本郡夫)。
集じん機のある工場では、集じん機本体も掃除する。集じん機を開けて、フィルターにたまった粉じんをバケツに受ける作業では、一気に粉じんを浴びた(江城正一、佐藤健一)。集じん機のダクトの中に入って掃除したら粉じんまみれになった(岡本郡夫、簑田努、藪内昌一)。
(以下筆者注)
石綿紡織業の派生業種として、落綿関連の仕事があった。落綿(オチワタ)とは、石綿紡織の工程で生じる石綿の屑である。落綿関連の仕事として、落綿を集めて分別し石綿紡織に還元再利用する作業、落綿をスレート用に再生させるスレート混綿作業、さらにその材料であるスレート廃材の破砕作業があった。これらの作業は、いずれも直接に石綿(屑)を扱い、それをスコップや手で掬(すく)って袋詰めする作業であり、石綿紡織業よりさらに劣悪な作業環境下で行われたようである。青木善四郎は、もうもうと粉じんが舞い、向かい側に立っている人の顔が見えなくなるほどだったと言い、湖山寿啓の妻幸子は、1メートルくらい近づかないと顔がわからなかったと言う。「これが人間のする仕事か?」。法廷での彼女の証言である。
■粉じんの中の子育て
石綿の作業は、長時間労働だった。休みは通常日曜だけで、1日12時間以上働いたこともあった。
岡田春美は、午前7時から午後7時まで12時間働いて、いったん社宅に帰り、夕食の支度をして1時間ほどでまた工場に戻り、夜の10時頃まで仕事をした。休日は月に1、2回程度。繁忙期には、徹夜で翌日昼まで続けて作業をすることもあった(濱野石綿)。
古川昭子の労働時間は、基本的には平日の朝7時から夕方5時だったが、忙しいときは夜10時頃まで残業した。夕方いったん家に帰り、子どもの晩ご飯の世話をして仮眠をとり、夜中の12時から翌朝5時まで仕事をしたこともあった(濱野石綿等)。
西村東子の労働は朝5時から夕方5時までで、昼休みは15分、それ以上休むと給料から差し引かれた(日光アスベスト)。労働時間が長いということは、石綿粉じんを浴びる量もそれだけ大きいということだ。
子育て中の女性も、労働力として必要とされた。岡田春美は、人手が足らないからと社長に頼み込まれ、生後間もない陽子を粉じんの舞っている工場内のかごに入れて働いた(濱野石綿)。
原まゆみも、濱野石綿で子守をしながら仕事をした。幼児二人をかごに入れて混綿場の片隅においたり、うろうろしないよう二人の体を機械用のベルトでくくりつけた。カゴにはお菓子を入れておいた。子どもがぐずるときは、他の人に持ち場をみてもらって混綿場の綿の上で乳を飲ませたり、あやして寝かしつけた。
古川昭子も、繁忙期は、子どもを連れてでも来てくれと言われた。南石綿では、女工が子どもたちを連れてきて工場の中で遊ばせていた。まるで保育所のようだったと笑う。

■24時間粉じんに晒(さら)される
原告のうち13人が、石綿工場に隣接した社宅や寮に住んでいた。
青木善四郎は、大林石綿で、工場と同じ建物内に間仕切りしただけの部屋に住んでいた。ほこりまみれの服で出入りするうえ、工場の粉じんが部屋の中に入ってきていつもほこりっぽかった。原まゆみは、光石綿で、工場と同じ棟の2階の寮に住んでいた。1階は石綿工場、2階に石綿製品を保管する部屋と6畳ほどの寮の部屋があり、寮の片隅にもパッキンなどの石綿製品が置かれていた。寮に戻ると石綿のほこりがテーブルの上に溜まっていて、指で字が書けるほどだった。また井上石綿では、工場と社宅が同じ棟で混綿場との仕切りはベニヤ板1枚、ドアを開けると混綿場やカード機から勢いよく粉じんが入ってきた。
岡田春美らが勤めていた濱野石綿。ここから半径100メートル内に、米崎石綿、西河石綿、近畿アスベストの工場があった。濱野石綿と岡田春美一家が住んでいた社宅との間隔は1メートルほど、人一人がやっと通れるくらいだった。工場の窓は開けっ放しで、そこから石綿が吹き出していた。社宅の窓はとても開けられない状態だった。
古川昭子も濱野石綿の社宅に住んでいた。社宅と工場の窓が直接向き合うような形になっていて、社宅の窓を閉めていても、すき間から石綿のほこりが入ってきた。食卓にならべたハムにカビのように石綿のほこりが付いていることもあった。簑田努の住んでいた寮は、工場から5メートルほどの所にあった。寮の屋根や窓に石綿がたまって雪のようになっていた(簑田石綿)。
三好石綿では、1967(昭和42)年まで、敷地内に寮5棟があった。栄屋石綿には、工場と道をはさんで10軒ほどの社宅が並んでおり、工場の敷地内には寄宿舎もあった。
工場と住居が近いので、作業着に石綿の粉じんが付着したまま帰宅する者は多かった。入口でばたばたと粉じんをはたいて、幼い子どもたちを抱き上げた。工場と住居が近接しているために、仕事をしていないときにも石綿粉じんにさらされることになった。
■地域全体がひとつの「石綿工場」だった
石綿粉じんは、工場の外へも飛散した。
栄屋石綿の近辺は、近所の子どもたちの格好の遊び場だった。工場の窓から白い綿がふわふわ出ていた。工場沿いに走る阪和線の軌道には綿状の物質が雨にぬれてこびりついていた。昭和30年代近くに住んでいた筆者の目に焼きついている光景だ。
1976(昭和51)年に岸和田労基署に寄せられた電話記録には、「屋根といわず、外の溝といわず、石綿で真っ白である。これでは企業と監督署はグルと言われても仕方がない」とある(岸和田労基署資料)。
石綿工場付近の田んぼの畦道が石綿で真っ白、というのは当地ではごく普通の気に留めることもない風景だった。栄屋と並ぶ規模の石綿工場だった「三好石綿」。ここに隣接して米作りをしていた南寛三も被害者だ。泉南地域全体がひとつの大きな「石綿工場」だったと言っても、言い過ぎではないだろう。

■見えてきた被害の実態
泉南の石綿業に従事した者は押しなべて低学歴で貧しかった。労働組合はなく権利意識も低かった。不満を口にせず、また出来ず、長時間労働に耐えた。劣悪な労働環境下で黙々と働くだけだった。
一方地方出身者にとって、社宅のある職場は魅力だった。社宅から夫婦で出勤し、作業着のまま帰宅した。家でも石綿にさらされ、家族ぐるみの被害を受けることになった。
小規模零細な工場主は、排気・集じんの設備に金をかけようとしなかった。資金の関係でやりたくても十分には出来なかった。結果、劣悪な労働環境は放置・温存され、被害は蓄積した。