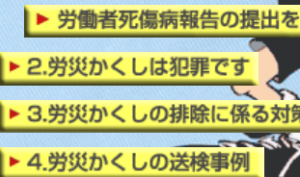慢性有機溶剤中毒による二次災害(めまい、失神による転倒骨折)に業務上認定
中島光孝(弁護士)
1998年10月30日、Oさんは一人、神戸地方裁判所第204号法廷において、森本裁判長が「被告は昭和61年7月11日付けで原告に対してした労働者災害補償保険法による療養補償給付の不支給処分を取り消す」、と判決文を読み上げるのを聞いた。原告・Oさんが被告・加古川労働基準監督署長に勝訴した瞬間であった。
この裁判は、当初の業務上の疾病である有機溶剤中毒症の療養中に発生した転倒による骨折等の業務起因性を問うものであった。この日の判決は、当初の業務上の傷病と本件負傷(骨折等)との間に相当因果関係があるとしたものであるが、いわば二次災害の場合に相当因果関係を認めた数少ない例であると思われるので概要を紹介したい。なお、以下では因果関係の問題が中心であることを予めおことわりしておきたい。
●経過
Oさんの勝利への経過を簡単に示すと次のとおりである。
1967年3月明石市内の会社に就職し、有機溶剤(トリクロルエチレン(別名トリクレン〉及び1,1,1トリクロルエタン)を使用する作業に従事した。
作業開始後間もなくから、次第に頭痛、咽頭痛、めまいなどの症状となり、1977年9月5日付けで、1976年4月9日を発症日とする労災認定を受けた。なお、Oさんは、この頃から兵庫県勤労者医療生活協同組合神戸診療所に通院し、当初はI医師、その後は現在に至るまでK医師を主治医としてきた。K医師には裁判について多大な協力をいただいた。
1983年5月31日、自宅ベランダで布団を取り入れようとした際、めまい発作を起こして失神、転倒して左足を負傷した。翌日、外科医院を受診し、左第三中足骨骨折、左足関節捻挫等と診断された。
Oさんは、本件傷害にっいて、1984年2月7日付けで労災保険法に基づく療養補償給付を請求したが、1986年7月11日付けで加古川労働基準監督署長の不支給決定(本件処分)があった。これに対し、兵庫県労働者災害補償保険審査官に審査請求をしたが、1987月20日付けで棄却された。さらに、労働保険審査会に再審査請求をしたが、これも1993年3月24日付けで請求棄却の裁決となった。
1993年7月15日、Oさんは、神戸地裁に労災保険給付不支給処分取消請求を提訴し、本件処分の取消を求めた。そして、1998年10月30日、本件処分を取り消す旨の判決を獲得した。
●審査官
決定本件の最大の争点は、本件傷害が、業務上疾病である有機溶剤中毒症に不可避的に伴うめまい発作に起因するかどうかである。この点に関し、兵庫県労災保険審査官の前記決定は、次のように判断している。
- 平衡障害.眩量症状に対する特段の治療も検査も行われていない。
- 有機溶剤中毒の特有症状とされている造血器系の障害が血液所見より否定されている。
- 左足負傷で受診した外科医院において、意識そう失発作に関する治療は行われていない
- 血圧、脳波等関連検査の所見は正常である。
以上から、労災医員医師の「有機溶剤中毒の造血器系の障害による失神は、検査所見より、有機溶剤と因果関係がある失神とは考えがたい。」とする意見が妥当である。
しかし、この判断は、労災医員医師の意見に寄りかかりすぎたために誤ったものであった。労災医員医師の意見に基づき、有機溶剤中毒の特有症状は造血器系の障害である、したがって造血器系に障害がない場合には有機溶剤中毒症とはいえないとの固定観念ができてしまったために、このような判断になったものであろう。しかし、それは誤りである。
判決は、K医師や被告側証人のH医師らの証言をも証拠とし、「有機溶剤により造血器障害を起こすものがあるが、トリクロルエチレンや1,1,1トリクロルエタンは造血器障害を起こさないとされていることが認められる」としたのである。
●審査会裁決
労働保険審査会は、次のように述べて.M医師やK医師の見解を是認することはできないとしている。
「請求人(Oさん)は、本件負傷の時点で、有機溶剤職場から離脱して休業治療を受けてから約7年を経過しているにもかかわらず、請求人の申し立てる本件負傷前1年間の症状は、ばく露時の急性症状とされる症状が持続あるいは増悪しているやにみられるものであり、これは、一般の有機溶剤中毒症の経過とはかなり異なるものといわざるを得ず、低血圧気味の請求者の素因や有機溶剤中毒症り患に伴う心因反応の要素も考慮すべきであって、めまい、意識喪失を含め、請求人の申述する症状のすべてを直接有機溶剤中毒によるものとすることは困難である。」
この裁決は、Oさんの「低血圧気味の素因」や「有機溶剤中毒症り患に伴う心因性の反応の要素をも考慮すべきであるとしながら、実は何もそうした考慮をせず、因果関係を否定している。
●労災認定における因果関係判断の問題
上記審査官決定及び審査会裁決から、労災認定における因果関係判断の問題が浮かび上がる。
一つには.労災医員医師の意見に依拠しすぎていることである。二つには、因果関係の立証を被災により心身ともに苦しむ労働者に要求しすぎていることである。
第一の点は、本件に即して言えば、次のような経過があった。
すなわち、審査官決定が労災医員医師の意見(造血器系障害の有無の点)に大きく依拠していることを知ったK医師やOさんらが、労働基準局に見解を質したところ、労災医員医師の上記見解は間違いである旨の回答を得た。さらに再審査請求の場で「兵庫労基局では労災医員医師の意見について、こういうふうに言われた。」と言えば審査会も認めるでしょうという趣旨のことを言われた。Oさんは、これに勇気を得て再審査の審問の際経過を説明したのであるが、結局は審査会は審査官が労災医員医師の意見に依拠していた点を特に考慮することなく、やはり労災を認めなかったのである。これでは、はじめから結論が決まっていたと言われても仕方がないであろう。
第二の点は項を改め述べる。
●因果関係の立証の問題
本件裁判で、被告は、「業務起因性を認めるためには、業務と疾病等との間に条件関係が認められるだけでは足りず.法的に見て労災補償を認めるのを相当とする相当因果関係が必要である」と主張した。労災裁判では、労基署長が必ず行う主張であり、それ自体目新しいものではない。
一般に、「相当因果関係」という用語は刑法の世界で使用され、その意味するところは、一般人の社会生活上の経験に照らして通常その行為からその結果が発生することが「相当」と認められる場合に刑法上の因果関係を認めるというものである。
その趣旨は①条件関係(あれなくばこれなし、という関係)のあるものから不相当な場合を排除することにより刑法上の因果間関係を限定する点と、②作為時を基準に、一般人の目で見て相当性を判断する点にある。
刑法においては、「疑わしきは被告人の利益に」とか「刑法の謙抑性」と言われ、処罰範囲が拡大することを制限する解釈がとられる。このため、因果関係の判断においても、犯罪の成立範囲が拡大してしまう条件関係だけで足りるとするとの見解ではなく、「相当」な因果関係まで必要だとする相当因果関係説が通説となり判例となっているのである。
そこで、刑法以外でも因果関係が問題となる場合には、一般に「相当因果関係」まで必要だとされ、労災における行政実務あるいは裁判においても、業務と疾病との間に相当因果関係がなければ業務起因性は認められないとされてきたのである。
しかしながら、刑法と労災補償制度とは、その指導原理を全く異にする。刑法は処罰範囲を限定するために「相当性」を要求する。しかし、労災補償制度は可能な限り被災労働者に対する補償範囲を拡大するところにその真骨頂がある。刑法においては、国家ができるだけ個人に介入することを抑制することによってその自由を保障しようとするのに対し、労災補償制度においては.国家が個人(使用者と労働者)に介入し、労働者の立場に立って労働に必然的に伴う災害による損失をできるだけ補償しようとしているのである。
したがって、補償範囲を限定する機能を持つ「相当性」を労災補償制度に持ち込むことは、労災補償制度の本来の趣旨を損なうことになる。現に被告も、補償範囲を拡大しては使用者に過大な負担を強いることになると主張していたのであるが、それは制度本来の趣旨に全く背を向けたものといわなければならない。
被告の主張によれば、被災労働者の側で「相当因果関係」を立証しなければならない。しかし、上記のとおり、そもそも「相当因果関係論」そのものに疑問があるうえ、自動車事故の被害者救済を目的として立法化された自動車損害賠償保障法3条(加害者に無過失の立証責任があるとした〉や公害患者が疫学的因果関係の立証をすれば公害企業側で因果関係の不存在を立証しない限り「相当因果関係」の存在が認められるとした判例(冨山イタイイタイ病判決)等の存在を考慮すれば、労災裁判においても、被災労働者が業務と疾病との間の条件関係を立証しさえずれば、労基署長の側で当該疾病が偶発的に生じたものであることを立証しない限り、「相当因果関係」を認めてしかるべきである。
今回の判決は、基本的には従来の「相当因果関係説」の立場にたっている。ただ、今回の判決は「本件骨折の主要な原因は骨粗霧症も考え得る」との被告の主張に対して、「原告に骨粗霧症があると認めるべき証拠はない」旨判示している点が注目される。仮に、前記審査会裁決のように、相当因果閥係の立証責任を原告に過酷に要求する立場に立てば、「骨粗鬆症の疑い」があるとの被告の主張により「骨粗鬆症があるとの心証」を抱かなくても、「骨粗鬆症の疑いがあるとの心証」を持っただけで、「骨粗鬆症の疑いも否定できず、相当な因果関係があるとまではいえない。」という趣旨の判示になっていた可能性がある。このような判決が予測される場合、原告としては裁判進行中、「骨粗鬆症はない」旨のおよそ不可能な立証活動を強いられることになる。その意味では、本判決は相当因果関係の立証の負担を原告被告双方に適切に振り分けたものと言うことができる。
●いわゆる二次災害における因果関係の判断の構造
本件の困難性は、有機溶剤中毒症→めまい→転倒 → 骨折の流れが因果関係で結ばれているかという点にあった。この点、被告は次のような場合でなければ因果関係は肯定できないという。
- 「当初の業務上の傷病が生じなかったならば、(業務外の災害も生じなかったであろうし、この災害が生じなかったなら1お現在の死傷病も生じなかったであろう」と認められ、かつ、「当初の業務上の傷病が生じなかったならば、かかる災害が生じたとしても、現在の死傷病は生じなかったであろう」と認められる場合
- 当初の業務上の傷病が生じなかったとしても、業務外の災害は生じ得たであろうが、この災害が療養中に通常生じうるもの又は避けられないと認められ.かつ、「当初の業務上の傷病が生じなかったならば.この業務外の災害が生じたとしても、現在の死傷病は生じなかったであろう」と認められる場合
被告は、右の1.と2.のいずれにもあてはまらない場合には、現在の死傷病は当初の業務上の傷病と相当因果関係がないとし、さらに次のいずれかの場合は相当因果関係がないとする。
- 条件関係すらない場合。
「当初の業務上の傷病が発生しなかったとしても、現在の死傷病は生じたであろう」という場合。 - 条件関係しかない場合。
「当初の業務上の傷病が生じなかったならば、現在の死傷病も生じなかったであろうが、当初の傷病が生じなかったとしても、この業務外の災害が生じたならば現在の死傷病は生じたであろう」という場合。
あるいは、「当初の業務上の傷病が生じなかったならば、業務外の災害が生じたとしても、現在の死傷病は生じなかったであろうが、当初の業務上の傷病が生じなかったとしても、業務外の災害は生じ得たであろう」と認められ、かつ、その災害が療養中に通常生じうるもの又は避けられないものと認められない場合。
この一見複雑な因果関係判断の構造は、二次災害であるが故のものであろう。問題は、ここでも原告、被告のいずれに立証責任があるかである。被告は、原告に立証責任があることを前提に「原告のめまいは有機溶剤中毒症によるものではなく、更年期にある原告の起立性低血圧によるもの」あるいは「アルコール摂取によるもの」あるいは「骨粗鬆症によるもの」などと主張し、かつ、原告の立証活動が不十分であるとして、前記1.2.のいずれにも該当しない旨主張した。この点に関し、本判決は以下のとおり判示した。
- 「本件めまいの原因は、有機溶剤中毒症により生じた脳幹障害にあると推認できることからすると、当初の業務上の傷病である有機溶剤中毒症が生じなかったならば、本件めまいは発生せず、本件傷害も生じなかったであろうといえるのであって、業務と本件障害との間には条件的因果関係があると認めることができる。」
- ①「有機溶剤中毒症に罹患すれば、その療養中に、有機溶剤中毒症の中枢神経症状としてのめまいのために転倒することは、通常あり得ることであると考えられる。」
②のみならず、「一般に、身体の転倒事故が生じても、咄嗟に手を付くなどの防御反応を取るため、すり傷やあざ程度で済むことが多く骨折等にまで至ることは少ないと考えられるところ、原告は、本件転倒の際、有機溶剤中毒症による本件めまい及び失神のために何ら防御反応を取ることができず、そのために急激に大きな衝撃を受け本件傷害にまで至ったものとみるのが自然である」から、業務と本件傷害との間には相当因果関係もあると認めるのが相当である。
右判示の中では2.②に注目すべきである。仮に、裁判官が「身体の転倒事故が生じた場合、すり傷やあざ程度で済むこともあるが、骨折等に至ることも少なくない」というのが経験則であると考えていた場合、本件判決の結論には至らなかった。裁判官が「身体の転倒事故により骨折等に至ることは少ない」ことを経験則とみたからこそ、Oさんが骨折したのは、本件転倒の際有機溶剤中毒症によるめまい及び失神のために防御反応を取ることができなかったからであるとの結論に至ることができたのである。この部分は判決全体の中では短い部分であるが、しかし、本判決の核心といってよい部分である。
結果的に、今回の判決は被告が提起した二次災害の判断枠組みを使って、Oさんの主張を認めたものとなった。
●最後に
裁判では、因果関係立証責任の負担軽減の主張を通じて.業務上疾病概念の拡張を主張した。しかし、従来の司法判断を無視するわけにもいかず、原告の側で相当程度の因果関係の立証をしなければならなかった。難しかったのは、二次災害の場合、どのような事実を提示すれば因果関係の立証活動になるかという点であった。
有機溶剤中毒症の罹患前にはめまいがなかったが、罹患後には継続的にめまいがあったこと、本件傷害も間断なく続いためまいの一つによって生じたものであること、めまいによる転倒によっては通常骨折まではいかないが、有機溶剤中毒症に罹患しているOさんの場合は咄嵯の防御活動ができなかったために骨折までいってしまったことなどをOさんの闘病日誌等を証拠として主張した。また、被告の医学的な主張に対しては全面的にK医師に依拠し反論してきた。
原告であるOさんの熱意とK医師のバックアップによって、納得できる判決を得ることができた。感謝したい。本件は、二次災害の場合の因果関係の判断について、一つの参考事例を提供するものである。本稿が何らかの参考になれば幸いである。
1999年3月31日記<労働者住民医療No.111-113>
安全センター情報1999年9月号