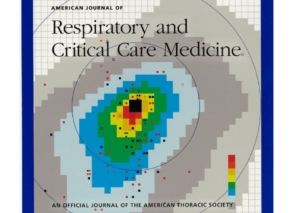労災保険のメリット制の廃止で17%の保険料引き下げが可能~「新たな検証結果」も存続を正当化せず
目次
メリット制に関するこれまでのデータ
労災保険のメリット制に関しては、「労災保険事業年報」に、継続・一括有期・有期の区分別、都道府県別、業種別、保険料増減率区分(±5%刻み)別の適用事業場数が紹介されているだけで、メリット制の労災保険財政に対する影響に関するデータは、まったく公表されていない。
これまで唯一の例外は、2010年12月7日の第2回労災保険財政検討会に示された「労災保険のメリット制について」という資料で、「試算によると、メリット制があることで平成20[2008]年度の保険料は差し引き1,871億円減少(保険料の約17%に相当)している」と書かれている。労災保険事業年報によれば、同年度の保険料徴収決定済額は1兆1,037億円だから、1,871億円は17.0%に相当する。
同年度のメリット制適用事業場数は120,419で、同年度末労災保険適用事業場2,632,696の4.6%。そのうち、労災保険率(料)割引きが103,231で、メリット制適用事業場の85.7%及び労災保険適用事業場の3.9%(据置きが1,858で各々1.5%及び0.0%、割増しが15,330で12.7%及び0.6%)であった。引上げ総額をX億円とすると、引下げ総額は「1,871+X」億円となる。しかし、Xの数字は示されておらず、引上げ総額と引下げ総額の差し引きが1,871億円の引下げであったということになる。
また、同検討会には、「継続事業 メリット増減率+40%・▲40%の賃金総額規模別構成比」も示され、2011年3月4日公表の検討会中間報告にも収録されているが、▲40%割引き適用の事業場の32%が賃金総額100億円以上の事業場であった。
その後、宮本徹衆議院議員の「メリット制に関する質問主意書」に対する2024年6月27日の政府答弁で、「令和3[2021]年度において、労災保険法が適用されている事業場数に対するメリット制が適用された事業場数の比率は5%となっており、また、同年度においてメリット制が適用された事業場の労災保険料の総額は、当該事業場に、メリット制が適用されなかったとした場合に事業主が支払うべき労災保険料の総額を1,500億円程度下回るものと試算している」というデータが示された。
同年度のメリット制適用事業場数は146,320で、同年度末労災保険適用事業場2,950,453の5.0%。そのうち、労災保険率(料)割引きが121,188で、メリット制適用事業場の82.8%及び労災保険適用事業場の4.1%(据置きが2,312で1.6%及び0.0%、割増しが22,820で15.6%と0.8%)であった。
同年度の保険料徴収決定済額は8,610億円だから、1,500億円は17.4%に相当する。
メリット制に関する新たなデータ
2025年4月4日の第5回労災保険制度の在り方に関する研究会に、「メリット制について」新たな資料が提出された(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56726.html)。これによれば、令和5[2023]年度にメリット制が適用された事業場数は147,302事業所であり、以下のような内訳であった。
・ 保険率(料)割引きが121,770事業場(全メリット適用事業場の82.7%)-引下げとなった差額保険料▲1,767億円(メリット制適用前保険料が6,076億円とのことなので平均29.1%の引下げ、実際には58.2%(70,904事業場)が▲40%の引下げ)
・ 保険率(料)据置きが2,370事業場(全メリット適用事業場の1.6%)
・ 保険率(料)割増しが23,162事業場(全メリット適用事業場の5.7%)-引上げとなった差額保険料+195億円(メリット制適用前保険料が852億円とのことなので平均22.9%の引上げ、実際には48.7%(11,288事業場)が+40%の引上げ)
結果的に全体では、引下げ▲1,767億円+引上げ195億円=▲1,572億円の引下げだった。資料には、「メリット制の適用により引下げとなる保険料分を見越し、労災保険率を引き上げて設定している」と記載されている。
令和5年度の保険料徴収決定済額は9,260億円なので、1,572億円はその17.0%に相当する。これは、前出の2008年度の数字17.0%及び2021年度の数字17.4%程度とほぼ一致している。
同年度末労災保険適用事業場数2,972,468に対するメリット制適用事業場数147,302の割合は5.0%で、割引き事業場数121,770の割合は4.1%(割増し事業場数23,162の割合は0.8%、据置き事業場数2,370の割合は0.0%)である。これらも、2008年度の数字及び2021年度の数字とほぼ一致している。
メリット制の労災保険財政への影響
すなわち、全事業場のわずか4%にすぎない事業場が割引きを享受(及び1%未満の事業場に対する割増しの賦課)することと引き換えに、労災保険料が17%引き上げられている(17%の引下げを全事業場が肩代わりしている)ということである。
肩代わりさせられている全事業場の95%以上に当たるメリット制非適用事業場は、いかに労災防止努力を行い、また実際に労災を減少させていたとしても、割引きを享受する機会すら与えられていない。
厚生労働省は、メリット制を、「保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止の一層の努力を目的」としたものと説明するが、実態は大きな不公平を生み出している。しかも、実態を示すデータは、ここに紹介した過去3回しか公表されたことがない。
逆に、メリット制がなければ、労災保険料を17%引き下げることができる。この恩恵は、全事業場の96%が享受することができるのである。
なお、全事業場に対するメリット制適用事業場の割合について、提出された資料は、継続事業について年度当初適用事業場数2,296,419に対するメリット制適用事業場数83,275の割合として3.6%、一括有期事業について年度当初適用事業場数621,846に対するメリット制適用事業場数27,123の割合として4.4%、有期事業について当年度消滅事業場数40,886に対するメリット制適用事業場数36,904の割合として90.3%という数字を示す一方で、次のようにも書いている。
「令和5年度にメリット制が適用された継続事業及び一括有期事業場数は約11万事業場であり、全ての継続事業及び一括有期事業場数約291万事業場に対して、約4%のメリット制適用割合となっている。一方で、労働者数でみると、令和5年度にメリット制が適用された継続事業及び一括有期事業場の労働者数は約3,563万人であり、全ての継続事業及び一括有期事業場の労働者数約6,078万人に対して、約59%のメリット適用割合になっている」。
メリット制の効果の新たな検証結果
第5回労災保険制度の在り方に関する研究会に提出された資料には、「メリット制の効果について、メリットが適用されている事業場の被災者数増減率に着目して検証を行った」結果も示されている。概要は、以下のとおりである。
【検証方法】
全事業場とメリット適用事業場で被災者数の増減率を比較した。メリット適用事業場の被災者数の増減率が全事業場のそれと比べて小さければ、メリット制により被災者数の増減率が抑制されたとして、メリット制の効果があると考えられる。
検証では、
- 労災保険の収支率が比較的高く、メリット増減率がプラス(保険率割増)であるメリット適用事業場
- 労災保険の収支率が比較的低く、メリット増減率がマイナス(保険率割引)であるメリット適用事業場
に区分して被災者数の増減率を集計。
また、被災者数の増減が偶然の要素からもたらされないように、一定以上の労働者数が見込まれる6業種[建設事業、製造業、運輸業、ビルメンテナンス業、卸売業小売業飲食店又は宿泊業、金融業保険業又は不動産業]に限定して増減率を比較。
【検証結果】
- プラスでメリット制が適用された事業場については、全事業場よりも増減率が概ね低いことから、一定程度はメリット制の効果があったと考えられる。
- マイナスでメリット制が適用された事業場については、業種全体よりも増減率が低い場合と高い場合が同程度混在しており、これだけをもってメリット制の効果の有無を判断できるものではない。
ただし、マイナスでメリット制が適用された事業場は、過去の保険収支が良かった(≒災害が少なかった)ことや、もともと被災者数が0である事業場割合が多いため、これ以上被災者数を減らすことができない事業場であることを考慮する必要がある。
割引き事業場についての検証結果
詳しいデータについては、原資料を当たっていただきたいが、仮に全事業場よりも増減率が低かったとしても、まず、それがメリット制の効果であったかどうかは別途検証されなければならない問題であり、メリット制の効果が検証されたことにはならない。
「死荷重損失(dead weight loss)」効果として議論されることもあるようだがメリット制がなかったとしても労災防止努力をしていた可能性はあり、メリット制がなくても労災防止努力をする者が割引きの利益だけを享受することは、「フリーライダー(free riders)」問題としても議論される。まだ改宗していない者を改宗させるという本来の目的を果たせずに、「改宗者に説教する(preaching to the converted)」だけになるおそれも指摘されている。
今回の検証結果はこうした問題に答えるものになってはいないが、「マイナスでメリット制が適用[割引き]された事業場」についての結果は、労災防止努力の有無にかかわらず割引きが適用されている実態を反映している可能性があると解釈した方がよいように思われる。「マイナスでメリット制が適用[割引き]された事業場」についての結果は、メリット制の存続を正当化する根拠にはならない。
OSH WIKIが、「フリーライダー効果を低減するためには…法的労働安全衛生要求事項を満たしているということだけで報酬を与えられるべきではない」と指摘していることは重要であろう。
割増し事業場についての検証結果
他方、メリット制が使用者に、「請求の提出を妨げまたは抑制し、積極的な情報の差し控え、請求に反対し、請求者に有利な決定に不服を申し立て、請求者に早期の職場復帰を迫り、請求者に対する個人医療情報を求め、請求者にさらなる医学的検査を要求するなどの経済的インセンティブを与える」ことは、ILO Encyclopediaでも指摘されている。
厚生労働省は、「メリット制が労災隠しを助長する」という指摘に対して、①証拠がない(検証されていない)、②公共工事の指名停止等をおそれることなど複合的な要因が考えられる、と反論するのが常で、いまにいたるも負の影響の可能性の有無さえまともに議論も検証もしようとしていない。
「プラスでメリット制が適用[割増し]された事業場」についての今回の検証結果は、一方で、それが請求が抑制された結果でないことが確保されなければならないとともに、他方で、労働基準監督署による監督・指導等を含め、様々なインセンティブに基づく事業主や労使による様々な努力という複合的な要因によるものと解釈するのが妥当であろう。
仮に一定程度はメリット制の効果があったとしても、全事業場の1%未満の「プラスでメリット制が適用[割増し]された事業場」について一定程度の効果があったことをもって、圧倒的多数の事業場への不公平や、様々な負の影響を受け入れてまで、メリット制の存続を正当化する根拠にはならない。
OSH WIKIは、悪名高い過少申告企業には正の方向のインセンティブは効かないようだという「黒い羊(black sheep)」現象にもふれているが、まさに労災防止努力よりも労災請求を行った被災者を攻撃するような企業こそが、メリット制を口実に労災認定を争っている現実に照らして、労災保険のメリット制を廃止すべきである。
最新のILO報告書も労災隠しリスク指摘
最後に今年6月に開催される第113回ILO総会に向けて、2025年2月28日に報告書Ⅲ(B)「包括的な労働災害保護の達成」が提出されている。
この報告書で「経験率(experience rating)」にふれた部分をあるので、紹介しておきたい。
ひとつは、「第6章 労働災害の予防」の「6.2.1 インセンティブ」の以下の文章である。
348. 金銭的及び非金銭的インセンティブは、労働災害を防止する有効な手段となる可能性がある。認証、懸賞協議、品質マークなどの非金銭的インセンティブは、企業の優れたOSH慣行及び改善を認めるよう設計される。[以下省略]
349. 一般的な金銭的インセンティブ措置のひとつは、企業ごとに、当該企業で生じる傷害の頻度及び重度に応じて保険率[contribution rate]を個別に決定すること(経験率[experience rating、あるいは「経験査定」])である。例えば、チリでは、災害率の高い企業に対して、0.90%の保険率が最大6.8%まで引き上げられる場合がある。
350. 遡及的調整と将来的調整の両方が存在する。遡及的調整の場合には、使用者は、労働災害に関する提出された補償請求の件数に基づいて、年末に還付[refunds]または課徴[sur-charges]を受ける。将来調整のもとでは、保険率は、労働災害給付について提出された請求件数に関する以前の経験に基づいて決定される。経験率制度は、特定の業種のみまたはすべての使用者に適用される場合がある。
351. 保険率が、予防措置の実施状況に依存する場合もある。例えば、カボベルデでは、予防措置を実施している企業は、「労働災害及び職業病強制保険(SOAT)」の保険料を支払う際にボーナスを受け取る。トーゴでは、予防措置を遵守しない使用者に対して、保険率の引き上げが課される。リトアニアでは、予防措置を実施していない企業は、より高い社会保険料の支払いが義務づけられるグループに移行される可能性がある。
352. 委員会は、経験率が労働災害の防止にポジティブな影響を与える可能性があるものの、それは、そのような傷害に関する信頼できるデータと災害隠しのリスクを回避するための強力な監督メカニズムを必要とすることを強調する。さらに、個別保険率の決定には、より高額の管理費用を伴う、より進んだ管理システムとより訓練を受けた要員を必要とする可能性がある。
金銭的インセンティブは、補助金または助成金を通じて提供される場合もある。[以下省略]
もうひとつは、「第8章 労働災害保護制度の管理及び資金調達」の「8.2 労働災害給付の資金調達」の以下の文章である。
445. 経験率 [保険]率は、当該企業で発生する傷害の頻度及び重度を考慮して、各企業について個別に設定または調整される(例えば、南アフリカ)。この方法の主な目的のひとつは、労働災害の防止を確保することである。労働災害の発生を減少させるための予防措置の実施を促進するために、企業に対して保険率の引き下げが適用される場合がある。オーストラリア(南オーストラリア州)では、保険料の計算式に、無請求割引や良好な復職率に対する割り引きが含まれている。一方、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州では、保険率は、支払われた賃金の額、請求の発生、及び業種に基づいて決定される。同時に、経験率は、各使用者ごとの信頼できるデータベース、個別[保険料]請求を容易にする高度なツール、及び十分な訓練を受けた要員を必要とし、これにより管理費用が増加する場合もある。加えて、経験率は、労働災害の過少報告、予防からコスト管理への焦点のシフト及び訴訟の増加を招く可能性がある。
真の労災発生ではなく提出された保険請求の「経験」に基づく経験率=メリット制は、「労災隠し」のリスクをもちそれを「回避する強力な監督メカニズムを必要とすること」が強調され、「労働災害の過少報告、予防からコスト管理への焦点のシフト及び訴訟の増加を招く可能性がある」ことをはっきりと認めている。また、インセンティブには、非金銭的なものもあり、金銭的インセンティブも経験率に限られるものではないことなども示されている。
安全センター情報2025年6月号