自治体ごとに読影精度にばらつきー石綿読影の精度確保等調査継続
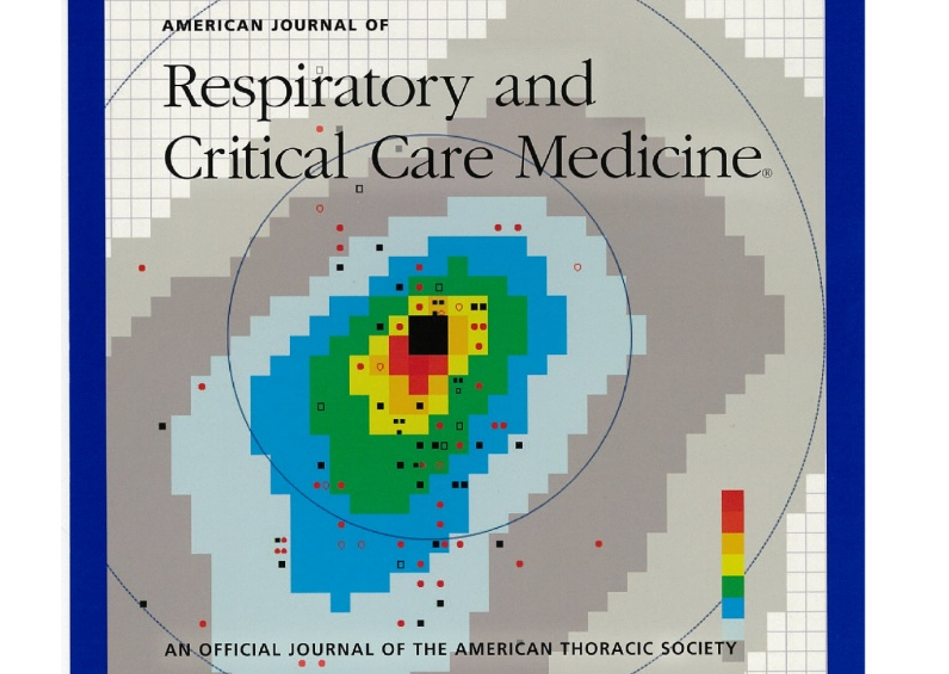
クボタショックからはじまった調査
2005年夏のクボタ・ショック後、アスベスト問題に関する関係閣僚会合がまとめた「アスベスト問題に係る総合対策」では、①「一般環境経由によるアスベスト曝露による健康リスクが高いと考えられる地域について、周辺住民に対する健康被害に関する実態調査」、及び、②「一般住民等の健康管理の促進」が掲げられた。
環境省は、石綿の健康影響に関する検討会を参集して、2005年度に兵庫県、2006年度には大阪府、佐賀県における「石綿の健康影響実態調査」を実施。尼崎市だけは「ばく露経路が特定できない[中皮腫死亡]者が多い」として「疫学的解析調査」も行い、「労働現場との関連以外の曝露による発症リスクが高くなっている可能性」を認めながら、それ以上の解明はなされなかった。鳥栖市と大阪府泉南地域については、「尼崎市のような、ばく露経路が特定できない者が相対的に多い地域を見出すことはできなかった」、「今後は、別途実施中の健康リスク調査等により、一般環境を経由した石綿ばく露による健康影響に関する知見について、引き続き収集に努めていく」とされてしまった。
「石綿のばく露歴や石綿関連疾患の発症リスクに関する実態把握」を目的とした「健康リスク調査」は、2006年度から尼崎市、鳥栖市、大阪府泉南地域で実施され、2007年度に大阪府河内長野市、横浜市鶴見区、羽島市、奈良県、2009年度に北九州市門司区が追加された。健康リスク調査は、第1期2006~09年度、第2期2010~14年度にかけて実施され、第2期では「石綿ばく露者の中・長期的な健康管理の在り方を検討するための知見を収集すること」が目的に加えられた。さらに、2015~19年度には、「従来のようにデータ収集を主な目的とする調査ではなく」、「石綿検診(仮称)の実施に伴う課題等を検討するためのフィージビリティ調査」としての「石綿ばく露者の健康管理に関する試行調査」を実施することとなり、検討会の名称も石綿ばく露者の健康管理に関する検討会に変えられた。これには、健康リスク調査参加自治体に加えて、2015年度に大阪市、堺市、芦屋市、西宮市、2016年度に東大阪市、八尾市、加古川市、2017年度にさいたま市中央区及び大宮区、2019年度にさいたま市の他の区、東京都大田区、宝塚市が加わった。
石綿検診(仮称)の実施も放棄
2020年3月「石綿ばく露者の健康管理に関する試行調査の主な結果及び今後の考え方について(最終とりまとめ)」は、「公共政策として検診モデルを積極的に推進する根拠は弱い」として、「石綿検診(仮称)の実施」は放棄されてしまった。
「しかし、石綿関連疾患は比較的まれな疾患であることから、民間の自発的な取組に委ねるだけでは、石綿ばく露者の健康管理の機会は十分に提供されない(読影できる医師が増えない、任意型検診の機会(人間ドックなど)が提供されにくい、など)と考えられる」ため、「既存検診が一つの機会として活用されることを想定しつつ、当面、読影体制の整備については、国が支援していくことが望まれる」。「具体的には、自治体が既存検診の画像を活用して石綿関連疾患の読影を行う場合、読影委員会等の機会を設けて専門家のサポートの下に実施することができるよう体制整備し、読影精度の確保のための知見の蓄積・普及を図ることが望まれる。また、石綿関連疾患の読影技術は、講習や経験のある医師からのフィードバック等を通じて一定程度の習得が可能であるため、既存検診にかかわる医師全般の読影技術の向上を図り、将来的には、既存検診の中で石綿関連疾患の読影も実施できるようにしていくことが期待される」とした。
また、「所見等から推定される過去のばく露に応じて」、①石綿の大量ばく露が推定される集団、②石綿のばく露が推定される集団、③石綿のばく露が不明な集団に分類し、②を、「広範囲の胸膜プラーク等の所見、じん肺法上の第1型以上の線維化の所見を有する者から成る」①「ほど明確な発症リスクは有しないが、職歴等や石綿関連所見の存在から、一定の石綿ばく露を受けた可能性が高いとみられる集団」として、「健康管理の在り方を検討する上での更なる知見の収集が望ましい。例えば、労働安全衛生法に基づく石綿健康管理手帳による健康管理を参考に、石綿関連疾患の早期発見が可能かどうか、といった観点で、追加的な検証を行っていくことが必要である」ともした。
①は「将来的に石綿関連疾患を発症する可能性が高いため、原則として専門医による個々の所見や症状に応じた経過観察の対象」、③については、「結核検診や肺がん検診など、既存のエックス線検査の機会を捉えて、石綿関連疾患が発見できるよう、体制を整備していくことが考えられる」、とした。
石綿読影の精度確保等調査
こうして、2020~24年度には、①「既存検診の機会を活用して石綿関連疾患を発見できる体制の整備に資するため、自治体の石綿読影の精度向上に向けた知見を収集することを目的とする『石綿読影の精度に係る調査』(「読影調査」)及び②「石綿関連疾患の早期発見、早期救済の可能性検証のための知見の収集を行うことを目的とする『有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査』(「有所見者調査」)からなる「石綿読影の精度確保等調査」が実施された。検討会の名称も石綿読影の精度確保等に関する検討会に変えられた。
「読影調査」は、参加自治体が実施する参加者の胸部エックス線検査画像について石綿関連疾患を念頭に置いた読影(「1次読影」)、及び、環境省(調査を請け負った事業者を含む)が実施する石綿関連疾患について十分な知識を持った専門家による読影(「2次読影」)から成り、1次読影と2次読影の結果を照合すること等により、自治体の石綿読影の精度向上に向けた知見を収集することとした。全国の自治体に参加を募ったが、2020~23年度に参加したのは37自治体だった※。
※【埼玉県】さいたま市、【岐阜県】羽島市、【大阪府】大阪市、堺市、岸和田市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、河内長野市、和泉市、東大阪市、泉南市、阪南市、熊取町、岬町、【兵庫県】神戸市、尼崎市、西宮市、【奈良県】奈良市、大和高田市、天理市、五條市、御所市、桜井市、平群町、三郷町、斑鳩町、田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、大淀町、下市町、吉野町、【福岡県】北九州市、【佐賀県】鳥栖市(一部の年度のみ参加した場合を含む)
「有所見者調査」は、環境省が、石綿関連所見を有する者を対象に既存検診後に追加して検査を行い、石綿関連疾患の早期発見、早期救済の可能性検証のための知見を収集した。対象となる石綿関連所見を有する者は、「胸膜プラークが胸部エックス線検査で確認できる場合(広範囲プラーク)」(石綿の大量ばく露が推定される集団)及び「石綿関連所見※が胸部エックス線検査で確認できる場合」(石綿のばく露が推定される集団)とされた。追加検査は、前者に対する胸部CT検査、及び、後者に対する胸部エックス線検査又は胸部CT検査、であった。
※胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、胸膜腫瘍(中皮腫)疑い、肺野の間質影、円形無気肺、肺野の腫瘤状陰影、リンパ節の腫大等
以下は、2025年3月「石綿読影の精度確保等調査の主な結果及び今後の考え方について」によっている。
2020~23年度の「読影調査」参加者数は延べ4,378人。1次読影を実施した者は4,333人で、うち829人が要精密検査※と判定された。2次読影を実施した者は3,504人で、うち401人が要精密検査と判定された。
※胸水貯留、胸膜プラーク、びまん性胸膜肥厚、肺野・縦隔の腫瘤状陰影、肺線維化所見、及びその他の所見(胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)、肺野の炎症後変化、線維化所見(じん肺I型程度に満たない線維化所見)、石灰化(胸膜プラーク以外)、結節・粒状影(炎症性結節など))
要精密検査と判定された者のうち、実際に精密検査として胸部CT検査を受けた者は延べ1,013人。胸部CT検査による精密検査の結果、石綿関連疾患の所見があり、「要医療」と判定された者は17人であった。その後の医療機関における診断結果等については本調査の対象外だ、17人のうち8人は翌年度以降に本調査に再度参加したことから、医療機関において経過観察と判定されたと推察される、としている。
1次読影方法別では、2,243人が読影委員会方式、2,135人が委託方式(うち2,123人は単独医師による読影、12人は複数医師による読影)であった。この点については、「読影精度の維持・向上のためには委員会方式が可能な自治体においては引き続き委員会方式を継続し、委員会方式が困難な自治体においては可能な限り過去画像を参照して比較読影を実施することが望ましい」等としている。
2020~23年度の「有所見者調査」の対象者延べ4,396人(読影調査参加自治体に居住する者4,333人、読影調査参加自治体に居住していない者63人)のうち、「石綿ばく露が不明な集団」は3,565人、「石綿のばく露が推定される集団」は193人、「石綿の大量ばく露が推定される集団」は638人であった。
読影調査に居住していない者63人のうち「石綿のばく露が推定される集団」は延べ3人、「石綿の大量ばく露が推定される集団」は延べ14人であった。そのうち延べ12人が追加検査を行った。その結果、「要医療」と判定された者はいなかった。
より詳しくは原文をあたっていただきたい。
新たな知見は確立できず
「今後の石綿ばく露者の健康管理の在り方について」は、②石綿のばく露が推定される集団だけでなく、①石綿の大量ばく露が推定される集団も調査に参加したことから、あわせて整理している。
「現時点では石綿ばく露者を対象とした中皮腫のスクリーニング方法は確立しておらず、肺がんについても本調査で広範囲プラーク等の石綿関連所見を有する参加者が繰り返し胸部CT検査を実施することで病変を発見できたのはわずかだったことを踏まえると、集団を対象として一律に毎年胸部CT検査を実施することは推奨されない。したがって、これらの集団についても、既存の胸部エックス線検査の機会を捉えて、石綿関連所見の変化や石綿関連疾患が発見できるよう体制整備を進めることが望ましい。
ただし、これらの集団の石綿関連疾患発症リスクは一様ではなく、喫煙歴や併存疾患等により異なると考えられることから、リスクの層別化に応じた健康管理の在り方について最新の知見を注視する必要があると考えられる。」
③石綿のばく露が不明な集団については、「結核検診や肺がん検診など既存の胸部エックス線検査の機会を捉えて、石綿関連所見や石綿関連疾患が発見できるよう引き続き体制整備を進めることが望ましい」、で変わりがない。
新たな知見は確立できていないということである。
「今後必要な対策について」、以下のとおり言う。
「前述のとおり、石綿ばく露者の健康管理は、既存検診の画像を利用して石綿関連疾患の読影を行うことを基本とするのが望ましく、将来的には、既存検診にかかわる医師全般の読影技術の向上を図り、既存検診の中で石綿関連疾患の読影も実施できるようにしていくことが期待される。
他方、本調査で明らかになったように、読影実施体制は自治体によって異なり、読影精度のばらつきがあることから、国の支援により体制の見直しやフィードバック等を通じて読影精度を均てん化することが求められる。本調査については、継続することを強く要望する声が複数の自治体から寄せられており、とりわけ過去に石綿を取り扱っていた施設が所在する自治体において参加者数が多い傾向にあったことを踏まえると、読影精度の向上や石綿読影の体制整備の観点から、当面の間、調査を継続して更なる知見を収集する必要があると考える。
なお、石綿ばく露者の石綿関連疾患の発症リスクは一様でなく、喫煙歴や併存疾患等によって異なると考えられることから、想定されるリスクに応じた健康管理の可能性については今後海外動向も注視しつつ検討していく必要があると考えられる。」
また、「おわりに」として、以下のように言う。
「令和2年度から開始した本調査では、調査参加自治体において石綿読影を行う体制整備を支援し、読影精度に係る知見を一定程度収集することができた点で意義があったと考えられる。本調査で明らかになった参加自治体ごとの読影精度のばらつきを踏まえると、引き続き自治体における石綿読影を行う体制整備の支援が必要であり、読影精度を向上させるためのより効果的で幅広い取組を模索する必要があると考えられる。
また、参加自治体の拡大については、幅広い自治体に対して調査の周知に努めたものの、各自治体における参加者数の伸び悩みもあり大幅な拡大にはいたらず、今後更なる検討が必要である。
今後、本取りまとめの内容を踏まえて調査を継続してさらなる知見の収集を行い、効果的・効率的な健康管理の在り方について必要な検討を続けていく。」
2025年度以降も調査を継続
したがって、「石綿読影の精度確保等調査」は、2025年度以降も継続されるものと考えられる。
日付けが示されていないが「令和7年度以降の健康管理について」と題された文書では、以下のとおり記載されている。
「これまでの議論を踏まえ、令和7年度以降の石綿ばく露者の健康管理については、以下の通りとしてはどうか。
一般住民については、既存検診(X線検査)を利用して石綿関連疾患・病変が発見できるような体制整備を引き続き行う。
○「石綿読影の精度に係る調査」を継続し、自治体の石綿関連疾患及び病変の読影の精度向上に向けた知見の収集及び普及を引き続き行う。
① CT検査については、これまで通りX線で要精密検査となった方を対象とする(※1)。
② 自治体での読影では、過去画像参照ありでの読影を可能な限り推奨し更なる精度確保を図る。
③ 環境省が選定した専門家によるCTの二次読影を継続する。
④ 二次読影所見をより効果的にフィードバックすることで読影の精度向上を図る(※2)。
⑤ 調査の周知や参加呼びかけをより効果的に実施し、更なる知見を収集する。
ただし、複数年参加者がCT検査を受ける場合の運用(※1)及びCT検査の二次読影結果をフィードバックする場合の考え方(※2)については今後の検討課題とする。
石綿の(大量)ばく露が推定される集団については、疾患の早期発見可能性に関する知見の収集を引き続き行う。
○ 「石綿読影の精度に係る調査」の参加自治体に居住する住民に関しては、同調査の枠組みにおいて既存検診(X線検査)を利用したフォローを行う。
○ 当該自治体からの転居者等については、「有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査」を継続し、フォローを行う。」
健康影響の実態を調査するから、健康リスクを調査するへ、次には石綿(検診)を見据えた試行調査へ、そして石綿読影の精度確保等へと、ずいぶん変わってきてしまっている。
アスベスト公害-住民の健康被害の実態を明らかにし、健康管理体制を確立することが、被害者・家族、住民だけでなく、関係自治体も含めた、共通の要望であることを忘れてはならない。
※関係資料:https://www.env.go.jp/air/asbestos/commi_hefc/index.html
安全センター情報2025年6月号


