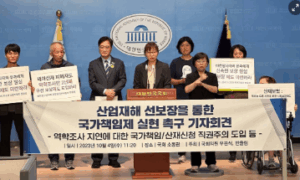増える職場内の葛藤、どこからが「いじめ」だろうか?/韓国の労災・安全衛生2025年10月5日

Aさんは午前6時26分、チーム長からカカオトークのメッセージを受け取った。出勤前だった。チーム長は記事のリンクを共有し、「教育庁は既に報道資料を出したんだな」と話した。これに対しAさんは、「えっ…」と応えた。チーム長は「えっ…ではなく、『直ぐに報道資料を準備して出します』と言うべきだ」と、Aさんを叱責した。
2019年に大田のある財団法人で、「職場内いじめ」として申告された事件だ。このように、業務時間外に業務に関するカカオトークを送るのも、「職場内いじめ」だろうか?
裁判所は違うと判断した。業務を「督励したに過ぎない」とし、インターネット記事の特殊性を考慮した時、迅速な報道資料作りが必要だということが認められるとし、業務上の適正範囲を越えなかったと判断した。
職場内いじめを禁止した改正勤労基準法が施行6年目を迎えたが、職場内いじめの被害者や使用者の側も、どこからを「いじめ」と認定すべきなのかを巡って、混乱している。下級審の判例が蓄積されている過程なので、明確な判断基準が確立されていないためだ。このような混乱は、申告と訴訟に繋がっている。職場内いじめの申告は2020年の5823件から、昨年の1万2253件に大幅に増え、公式の統計はないが、関連の民事・行政訴訟も増えていると推定される。
これに対し、雇用労働部も職場内いじめの判断基準を改善するために、この間の判例の動向を分析している。ハンギョレ新聞は「共に民主党」のイ・ヨンウ議員が、労働部から職場内いじめの判例分析資料を入手し、どのようなケースに職場内いじめが認められるのかを調べた。
公開的な叱責は「ケバケ」
労働部が韓国労働法学会に発注した委託研究報告書、『国内外職場内いじめ判断(判定、判例)など事例研究』を見ると、頻繁な公開的な叱責や侮辱・暴言は、職場内いじめと認められるケースが多かった。業務と一定水準の関連性があっても、大部分が業務上の適正範囲を越えていると見た。
具体的な事例を見ると、大学の行政室の主任が、他の部署の会計・庶務担当の期間制職員に、「恋人もできないの?(生まれてから一度も恋人のいない人)」「目が悪いんじゃないか」等、容貌を卑下したりするなどの言動をしたり、部下の職員が出張や休暇を報告しなければ公けに腹を立てて、会議の途中に「シーX(人の人格をけなす時に使われる卑俗語)」等の悪口を数回行ったケース、私立大学の科長だった教授が、学科の助教に、「基本的な業務なのに学ばなかったのか。イライラする。」「本当に気に入らないし、仕事もできずにイライラする」等の話を反復的に行った事例に対して、裁判所は全て「職場内いじめ」と認定した。特に、悪口の場合は、特定人を狙ったものでなくても、上級者が、職員たちが聞いているところで、続けて悪口の混ざった電話をしたケースも「勤務環境を悪化させる行為」と見て、「いじめ」が認められもした。
業務と直接的に関連した追及や叱責だとしても、公開的に行われ、被害者が侮辱されたと感じられるケースに、「いじめ」と認められた事例がある。青少年相談と福祉関連の政策研究をする法人で働いていたある相談士に対して、担当チーム長が、他の職員がいる前で、「なぜ私に直接報告しないのか」「相談はきちんとするのが正しいのか? どうして学生に週末に問題があったの? 相談への対応について話してみろ」と言って追及し、叱責したことを、裁判所は「いじめ」と認定した。
但し、公開的に叱責が行われにも拘わらず、「いじめ」と認定されなかったこともある。被害者の業務遂行能力が実際に足りないという情況や、相当な証明がされ、叱責の正当性が認められるケースだ。一例として、外傷センターで働いていた見習い看護師に対して、先輩の看護師が、質問に答えないという理由で大声を出して叱責したことに対して、裁判所は、被害者が救急室で受けた試験の成績が低く、ここで勤務する看護師には、高度な専門性と熟練性が要求されるということなどを考慮して、先輩の看護師が、教育目的を外れて暴言を吐いたとは見難いと判断した。
望まない私的連絡や私生活への干渉は大体認める
職場での職位や関係上の優位性を利用して、被害者に対する私生活に関連する情報を調べようとしたり、私生活に介入・干渉したり、自身と特別な関係を結んで、それを維持することを要求するなどの行為も、裁判所は「職場内いじめ」と見ている。
既婚の男性本部長が、同じチームの未婚の女性職員に、カカオトークで交際を要求し、これを断わると、業務中に怒ったり、自殺をして無断欠勤した事件。保育園の女性院長が、女性教師に下着の種類を特定して身体接触を試みたケース、出張に同行した部下の職員に、上級者が自分の家族の観光を頼んだケースなどが、裁判所で「いじめ」と認定された。
「いじめ」もよくある紛争のネタだ。裁判所で認められた「いじめ」の事例としては、被害者に向かってため息をついたり、露骨に無視する行動を繰り返したり、社内メッセンジャーで被害勤労者に対する悪口をやりとりしたケースがある。多数が少数を対象にしたり、上級者が下級者を対象にした「いじめ」に対しては、「職場内いじめ」を認めるのが一般的だ。しかし、下級者による「いじめ」も、状況を総合的に判断して「いじめ」と認定されることもある。不当解雇を争って復職した上級者を、部下の職員が業務指示のための団体チャットルームから強制退場させ、悪口を言った事件に対して、裁判所は「下級者だとしても、会社内の評判、世論などを利用して」上級者をいじめることもあるとし、職場内いじめと認定したことがある。
特殊雇用労働者は民事・刑事訴訟で解決しなければ
職場内いじめを禁止した勤労基準法76条の根本的な限界は、勤労基準法上の勤労者だけを保護の対象にしているということだ。このために、特殊雇用労働者など、勤労者でない労働者は、実質的に職場内いじめに該当する被害をこうむっても、勤基法上の保護を受けられず、個別的に民・刑事訴訟によって、権利救済を図らなければならない。判例を見ても、裁判所は「職場内いじめの被害者は必ず勤労者であるという必要はない」としている。
2025年10月5日 ハンギョレ新聞 ナム・ジヒョン記