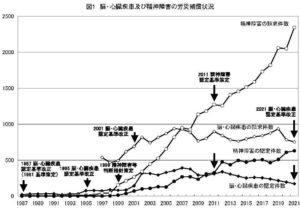「精神障害労災認定基準専門検討会」への申し入れ-2022年4月28日 全国労働安全衛生センター連絡会議・同メンタルヘルス・ハラスメント対策局
私たちは、職場のメンタルヘルスについて、30年余りにわたって、労働者の立場に立って、相談・対策にあたってきた団体や個人です。健康被害に至った場合には補償の問題となりますが、職場環境をはじめとする労働条件全般はもとより、予防対策についても話し合いで、必要に応じて労災請求や訴訟によって解決してきました。
残念ながら、長時間労働などによる過労やハラスメントによる精神疾患が後を絶ちません。そして、数字として表される労働時間ですら、その客観的な記録を怠る事業所が少なくありません。さまざまなハラスメントについては、事実関係はもとより、その客観的な評価が容易ではありません。現行の精神障害の労災認定基準は、抜本的な改正が必要であり、その運用にも大きな課題があると考えております。
本意見書も参考にしてくださり、よりよい労災認定基準を作成してくださるようお願いしたいと考え、僭越ではありますが、下記のとおり申し入れます。今後も専門検討会での議論を踏まえて意見を述べますのでよろしくお願いします。
目次
1 判例だけではなく、審査請求、再審査請求の原処分取り消し事案の分析を行うこと
今回の専門検討会に限らず、厚生労働省が労災認定基準を見直す際には、新たな医学的知見、職場の変化、裁判判例が契機となることが多い。それはそれで必要であり重要であることは間違いないが、労災認定基準の課題を検討するには、それを誤って解釈ないし運用したとして、労災保険審査官が労働基準監督署の原処分を取り消した事例、また、労災認定基準に拘束されないとされながらも、事実上認定基準に沿って労働保険審査会が原処分を取り消した事例の分析が非常に有効である。判断を誤った理由の中には、あまりにも稚拙な職員の怠慢なども見受けられ、判然としないこともあるが、実は労災認定基準そのものにも問題があり、労働現場の実態を十分に把握できず、結果として心理的負荷の評価を誤ったことも少なくない。
裁判所のような権限を持ち合わせていない労働基準監督署が、誤った判断を行わないために、これまでの裁決書と決定書の分析はもちろんのこと、当該審査官や署の担当職員の聴取も併せて行い、なぜ誤って不支給決定をしたのかをしっかり分析して、労災認定基準改正に役立ててもらいたい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11400000/000464376.pdf
例えば、厚生労働省の審査請求決定書事案を紹介した上記サイト(平成29年10月~平成30年3月)に紹介されている事例で、原処分庁は意見書で「上司及び同僚より、物を投げられたり、大声で怒鳴られているところを事業場関係者に目撃されているが、請求人が言い返す姿も目撃されており、請求人は一方的に嫌がらせを受けていたとは言えず、客観的に認識されるトラブルがあった」という判断をしていた。しかし審査官は、「上司及び同僚から、人格を否定する発言を継続的かつ頻繁に受けていたこと、物を投げつけられることが度々あり、これは、大けがに繋がりかねない行為であり、当該行為に対して請求人が言い返したことは、自己防衛であったと認めるのが相当である」として、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」を適用すべきであるとした。
請求人がひどい嫌がらせ、いじめ、暴行に当たると主張しているもかかわらず、上司とのトラブルという過小評価にしたことは明らかである。こうした事例はめずらしくない。嫌がらせの態様や頻度などについて原処分庁は調査をしているはずであり、審査官の把握した事実とどの程度の相違があったのかは、公開された決定書からは判断できないが、「言い返している」から一方的な嫌がらせではないというのはあまりにも稚拙な判断である。パワーハラスメントの「いじめ」と「トラブル」なのかの判断基準があいまいであることに起因する。また、パワーハラスメントであっても、「執拗」を要件としながら、その具体的な基準がはっきりしない。
2 労働時間の事実認定、評価を適切に行うこと
① いわゆる待機時間について
運転労働者以外は、通達等でもその位置付けが不明確で、しばしば労働時間として算定されないことがある。もちろん休憩室等で寝ている場合や、外出が許されているような場合と、運転労働者の荷待ち時間を同列に扱うことはできないが、少なくとも居場所が特定されていたり、すぐに対応が求められる状態である場合は、原則としてすべて労働時間として扱うべきである。
数年前に新宿労働基準監督署で役員付運転手の過労死事案で、日中の社内における待機や、夜の宴席の際の待機について、全て休み時間だと決めつけて不支給決定した。ちなみにこの件の監督署担当職員は、不支給理由を尋ねる遺族に対して、「審査請求しても無駄ですよ」などと豪語していた。労働時間は賃金明細にも明記されており、事業主はそれに応じて賃金を支払っていたことから、解釈だけの問題で、よほど自信があったのであろう。その後、東京労働局労災保険審査官は、待機時間もほぼすべて労働時間と事実認定して原処分を取り消した。
② 出張における業務範囲
出張と言ってもさまざまであり、2時間の会議に出るだけで、観光旅行をしたり、会議後の宴席がメインのようなものも皆無ではない。現在のコロナ禍においては、そのような出張はなくなり、会議をオンラインで行われることも多い。しかしながら、出張先関係者に、いわゆる名所を案内してもらったり、宴席にしても、関係者の親睦を深め、それが商談や成果に結びつくからこそ許容されてきたものである。労働時間ではなく成果で評価される時代になればなるほど、人と人とのつながりはきわめて重要である。少なくとも費用を相手であれ自社であれ、会社が負担するものについては、すべて業務としてとらえるべきである。出張先での移動中も、宿泊先においても、メールのやりとりやパソコンで作業をすることは、きわめて普通のことであり、原則として、出発から帰宅まですべて業務ととらえるべきである。
③ 労働時間算定
テレワークについてはガイドラインも作成されているが、IT機器を使用していることがほとんどであることから、むしろ労働時間管理は容易である。労働者本人による申告制度を禁止していない以上、請求人側の主張を覆すような、客観的な証拠を雇用主側が提出できない限りは、原則として請求人の主張をすべて認めるべきである。
勤務時間外のメール、電話等の記録で業務遂行の時刻が明らかである場合でも、その時刻と時刻の間を労働時間として一切認めないような事例がしばしば見受けられる。もちろん労働者が帰宅後に入浴、食事をした後に、やっておかなければならないことを突然思い出してメールで連絡をしただけのような場合を除いて、基本的には請求人側の主張に沿って労働時間を認めるべきである。
書類等の成果物から、おおよその実労働時間が推定できる場合には、請求人や同僚等に尋ねて推定することを必須とすべきである。職場にいるにもかかわらず、私的な用事をしていただけだという主張をする使用者もいる。これについても、客観的な証拠(例えば、友人・知人への架電記録や趣味のサイトへのアクセスが大量にある場合など)がない以上、業務の必要性があったとみなして労働時間とみなすべきである。
④ 勤務間インターバルが短いなど勤務時間の不規則性について
脳・心臓疾患の認定基準においては、労働以外の負荷要因のひとつとして、「勤務時間の不規則性」が明示されており、「拘束時間の長い勤務」、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」があげられている。ところが精神疾患の認定基準では、心理的負荷が認められる出来事として、休日のない「2週間以上の連続勤務」のみが例示されているだけで、交替制勤務や深夜勤務についても、「勤務形態の変化」としてあげられているに過ぎない。「拘束時間の長い勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」は、それ自体が睡眠時間に大きく影響するものであり、心理的負荷は明らかである。心理的負荷が認められる「出来事」として把握するとともに、総労働時間数とともに適切に評価すべきである。
3 ハラスメントの評価
① 悲惨な事故や災害を目撃した場合
同僚が事故に遭ったり、ハラスメントを受けたり、自殺に追い込まれたりするのを見るのは非常に辛いものである。現行の例示では、「自らの死を予感させる程度の事故」、「被害者が死亡する事故」「多量の出血を伴うような事故」というような、悲惨さや災害の程度についてのみ基準のようなものが示されているが十分ではない。例えば、「被害者との関係」については何ら例示がない。まったく知らない被害者の交通事故に遭遇するような場合と比べて、自殺した同僚や部下が以前から請求人に助けを求めていた場合や、自殺の第一発見者がお世話になってきた特定の訪問介護士や看護師等である請求人になるようにされた場合など、より大きな心理的負荷があることは明白である。
② 第三者(家族、同僚、退職者など)による評価
ハラスメントの場合、「指導に過ぎない」加害者側の評価と、被害者側の心理的負荷が大きく異なることが少なくない。会社関係者の聴取は当然行われているが、労災と認めたくない会社に配慮して、真実を述べることに躊躇することが少なくない。事実関係やその評価については、会社と利害関係のない退職者や家族などにも十分な聴取を行って、適切な事実認定と評価をするべきである。
③ 無視(仲間外れ)の評価
職場で特定の人物、または集団に「無視される」という出来事について、きちんと評価してもらいたい。パワーハラスメントの定義の6つの類型のうちの「人間関係からの切り離し」にあたる。これまで取り組んだ事例でも、職場で直属の上司1人であっても長期に無視され続けて仕事に支障を来している場合や、集団に無視されている場合、しかも本人が派遣社員で派遣先の上司が加害者であり、誰に相談しても効果のある対策を取ってもらえなかった場合など、心理的負荷をさらに過重とする条件下であるににもかかわらず、評価を「弱」にされることがある。
4 退職強要と解雇について
労災保険に携わる職員は、いわゆる労使紛争に関わることは皆無である。暴行等の脅迫的手段を用いた退職強要は稀であり、例えば、懲戒処分や通勤が困難な異動をほのめかしたり、虚偽の情報提供などで退職に追い込むケースが多い。一部の経営者団体や弁護士、社労士などは、法律的に問題なく「ローパフォーマンス社員」をどう扱うべきか、「上手に辞めてもらう方法」などを指南している。こうした退職勧奨の実態をまったく考慮しない例示になっている。
解雇については、どれほど理不尽で心理的負荷が大きくても、文書で理由を明示してあれば「強」にはならないという例示内容である。そもそも請求人に納得できない解雇は退職強要に他ならず、解雇そのものが不当であればあるほど、心理的負荷が大きくなるが、そうした調査や評価は労災担当者には困難であり、認定基準に詳しく例示するべきである。
5 基礎疾患について
① 発症前しか評価しない
精神的な不調を訴える労働者が増えている一方で、受診を躊躇する労働者も未だに少なくない。そして、精神疾患の診断は難しく、治療の必要性の判断も同様である。きわめて短期間のストレスで発症することも少なくない。
いずれにせよ、請求人が、いつ発症したのかを判断することはきわめて困難であるにもかかわらず、診察すらしていない専門医員が、相当以前の段階から発症していたと決めつける判断が非常に多い。そのことによって、精神的不調にもかかわらず長期間にわたって懸命に働き、結果として長時間労働やハラスメントなどの職場のストレスにさらされ続けた労働者ほど認定されないという事態が生じている。
厳密な意味での医学的な発症時期の特定は不可能であり、むしろ評価の期間を発症前に限るという認定基準の枠組みそのものを変更することが必要である。実務的にも、通院も休業もしていない場合は、療養費も休業補償の請求も支給もあり得ないのだから、ストレスを受けた直後に受診したことが明らかな事例以外は、発症後の出来事も評価の対象とするべきである。
② 特別な出来事しか増悪を認めない
精神疾患の患者が増えている。通院しながらすばらしい仕事をしている労働者もいる。いわゆる発達障害の労働者も、特別な才能を有することもあり、それを活かして働く人も少なくない。
ところが、そういう人に仕事が集中したり、ハラスメントを受けて、休業を余儀なくされた場合、現行の認定基準では、「特別な出来事」でなければ認定されない。一口に基礎疾患、障害と言っても、精神的なものについてはその程度や症状はさまざまであり、一律にあるかないかで区切ることはあまりにも乱暴である。
なお、基礎疾患を治療していた主治医は、発症しているにも関わらず通院していなかった事例よりもはるかに継続して、請求人の症状について把握していることが多い。したがって、主治医が業務によって明らかに増悪したと判断した場合は、それを明確に否定する医学的な知見がない限りは、原則としてすべて業務上とすべきである。
6 複数の出来事の総合評価
出来事が複数以上ある場合で、それぞれの出来事が関連せずに生じている場合、それぞれを評価して「強」となる出来事はないとはいえ、「中」の出来事が複数以上となった時の総合評価を、「強」とする事案が非常に少ない。
大阪労働局に毎年確認しているが、毎年30件ほどの支給決定件数があり(令和2年度は51件だった)、関連しない「中」の出来事が複数以上あったことから結果として「強」と評価された事案は、毎年せいぜい1、2件、多くても3件である。複数の出来事がある事例は、非常に多いにもかかわらず、このように少ないのは、どのような場合に「強」と評価するのか、基準が示されておらず、判断が難しいためではないかと推察する。しかし、実際には被災者にとって、ひとつの出来事の評価が「中」でも、いくつも重なることによって心理的負荷が過重になる場合は多い。「強」の判断となった事案を例示するなどして、判断しやすいようにしてもらいたい。
7 労災の調査担当者の課題
労災認定基準そのものの問題が背景にあるとはいえ、あまりにも労災の担当職員が怠慢や誤りが目立つので、簡単に紹介する。
① 音声データを聞かない
ハラスメントについて請求人が証拠として音声データを提出したが、まじめに聴取せず、「聞き取り不能」と決めつけて判断材料にしなかったことがある。比較的低い価格(少なくとも増員するよりも)で文字おこしをしてくれる民間企業にある。きちんと予算を付けて反訳させるべきである。
② 医学的意見を十分に調査しない
主治医への質問と専門医員との判断が異なる場合がある。少なくとも病名まで異なる場合には、再度主治医に質問すればよいだけであるのに、それすらしないことが多い。診察もしないで病名を決めつけるのは、患者との信頼関係を損ねる恐れがあり、治療妨害になりかねないので、労災保険請求に協力したくないという医師もいる。
③ 成果物など資料の分析をしない
請求人が提出した仕事に関する資料をまったく分析しようとせず、単純に労働時間記録だけで長時間労働ではないと判断する事例が増えている。
④ 重要な関係者の聴取をしない
請求人が最も事実を知っている同僚などの聴取を求めても、決めるのは労働基準監督署だということで会社にとって都合のよい人だけの聴取を行うことが少なくない。そのことが再審査請求でようやく明らかになることもあった。すでに連絡を取ることができなくなっていることもある。
⑤ 本人聴取と会社聴取を別の人間が行うなど
ハラスメントなど請求人と関係者の言い分が異なることが多い。その場合は両方の言い分を同じ人が聞いて信憑性を判断すべきである。ところが一部の労働局では、本人聴取と会社関係者の聴取を別の人間が行っている。裁判所ですら尋問は同じ人が行うのに、それほどの権限もない労働基準監督署職員が手分けして行うことは正確な事実把握ができるはずがない。