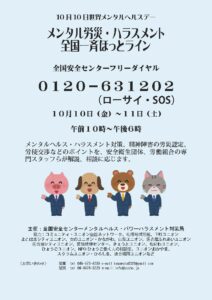遅発性疾病給付基礎日額さらなる改正を、メリット制は廃止を要望/労災保険制度の在り方に関する研究会中間報告書に対する意見
労災保険制度の在り方に関する研究会は、2024年12月24日からはじまった(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46695.html)。全国労働安全衛生センター連絡会議として、2025年3月5日付けで労災保険制度の在り方に関する研究会における検討について申入書を届けているが(2025年5月号)、同研究会が2025年7月29日に第8回を開催した翌7月30日に厚生労働省は同研究会の中間報告書を公表した。
全国安全センターでは8月5日付けで、あらためてこれに対する意見を厚生労働省に届けた。今後、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会における審議にあたって、同部会の委員に配布するとともに、厚生労働省自身にも参考としていただきたい。また、合わせて、同研究会の各委員にも配布するよう要望した。
目次
1.メリット制
中間報告書は、次のように結論づける。
「メリット制の効果については、様々な留保を前提とするとの意見はあるものの、一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点からもメリット制には一定の意義が認められるものと考える。また、労災かくしを助長するとの懸念についても、メリット制の意義を損なうほどの影響があるとは確認されなかった。
このため、メリット制を存続させ適切に運用することが適当と考える。
その際、今回の検証は初めての試みであり、今後も今回の検証において指摘のあった点も踏まえて、継続的に効果等を検証し、より効果的な制度となるよう必要な見直しを行うことが望まれる。」
しかし、第一に、不公平を正当化できるような効果は確認されていない。今回研究会に提出されたデータは、過去2回公表されたものと同じく、メリット制により労災保険率が高くなった事業場が全事業場の1%未満、保険率が低くなった事業場が約4%で、トータルで労災保険料全体の約17%に相当する割引になっている実態を明らかにした。メリット制がなければ労災保険率を17%引き下げることができ、圧倒的多数の事業場がこの割引分を肩代わりさせられている実態が再確認されたわけである。これに対して、研究会に提出された新たな分析結果は、労災保険率が高くなった事業場について「一定程度は効果があったと考えられた」が、保険率が低くなった事業場については「効果の有無を判断できるものではなかった」というもので、この不公平を正当化できる根拠になっていない。専門的には、メリット制がなかったとしても労災防止努力をしていた可能性はあり、メリット制がなくても労災防止努力をする者が割引の利益だけを享受することが「フリーライダー」問題として議論されている。まだ改宗していない者を改宗させるという本来の目的を果たせずに、「改宗者に説教する」だけになるおそれも指摘されている。厚生労働省の分析結果はこうした問題に答えるものになってはいないが、保険率が低くなった事業場についての結果は、労災防止努力の有無にかかわらず割引が適用されている実態を反映していると解釈することができよう。欧州労働安全衛生機関(EU-OSHA)が運営するOSHwikiが、「フリーライダー効果を低減するためには…法的労働安全衛生要求事項を満たしているということだけで報酬を与えられるべきではない」と指摘していることは重要である。
第二に、メリット制の負の影響について専門的に検討されていない。メリット制が使用者に、「請求の提出を妨げまたは抑制し、積極的な情報を差し控え、請求に反対し、請求者に有利な決定に不服を申し立て、請求者に早期の職場復帰を迫り、請求者に関する個人医療情報を求め、請求者にさらなる医学的検査を要求するなどの経済的インセンティブを与える」ことは、ILO Encyclopedia等で指摘されている。先日開催された第113回ILO総会に提出された条約及び勧告の適用に関する専門家委員会の報告書「包括的な労働災害保護の実現」でも、メリット制は、「労働災害の過少報告、予防からコスト管理への焦点のシフト及び訴訟の増加を招く可能性がある」と指摘されている。言わば、専門家にとって常識と考えられる知見にほぼふれることなく、事業主や被災労働者ではなく都道府県労働局を対象に行ったひとつの調査なるものの結果のみをもって、「労災かくしを助長するとの懸念についても、メリット制の意義を損なうほどの影響があるとは確認されなかった」という結論に専門家として合意できるのか不思議でならない。
第三に、新たな負の影響-メリット制適用対象事業主による労働基準監督署や被災労働者に対する圧力・攻撃が増加する可能性との関連でメリット制存続の是非が検討されていない。
中間報告書は、「労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について」として、「労災保険給付に関する決定の事業主への提供」を検討課題に取り上げた理由を、次のように説明する。「あんしん財団事件最高裁判決を受け、事業主が保険料認定の処分に係る不服申立てや取消訴訟の機会において労災保険給付の支給該当性について争えることが明確になり、今後は労災保険給付の支給に対する事業主の関心がより高まることが予想されるため、労災保険給付の支給決定に関する情報の、事業主への提供について検討を行った。」
「保険料認定処分に係る不服申立・取消訴訟を通じた労災保険給付の支給該当性についての争い」だけにとどまらず、労災保険請求自体及び労災認定調査のプロセス等を通じても、一部の事業主による労働基準監督署や被災労働者に対する圧力・攻撃が増加する可能性が想定されることは、前出のOSHwikiやILOの引用からも明らかである。「増加の可能性があるから、労災保険給付の支給決定に関する情報の事業主への提供について検討」するのではなく、「増加する可能性との関連でメリット制存続の是非を検討」すべきである。OSHwikiは、悪名高い過少申告企業には正の方向のインセンティブは働かないようだという、「黒い羊」現象についてもふれているが、まさに労災防止努力よりも労災保険給付請求を行う労働者を攻撃するような悪質な企業こそが、労働基準監督署や被災労働者に対する圧力・攻撃を行い、また、労災認定を争っているという現実に照らして、メリット制を廃止すべきである。
そもそも、無過失でも給付される強制加入保険で、保険料に労災補償給付の有無に応じた保険料のメリット制を入れること自体が合理的ではない。どんなに使用者が災害防止活動をしても労働者の重大な過失によって生じる事故や疾病はあり得るし、極めてずさんな労働環境を放置していても、現場労働者の努力で事故がたまたま起きずに済むことがある。負担の公平性や災害防止効果で言えば、企業規模に関わらず災害防止活動への参加の義務付け、どうしても参加しない会社には事業所名の公開や罰金を支払う(障碍者雇用率未達成企業と同様)といった制度の導入を検討するべきである。
2.労災保険給付の支給決定に関する情報の事業主への提供(労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題)
中間報告書は先の引用に続けて議論を紹介した後、次のように結論づける。
「労災保険給付の支給決定(不支給決定)の事実については、事業主が早期に災害防止に取り組む上で必要な情報であるとの点に加え、事業主の保険料負担が労働基準法の災害補償責任を基礎としている点、事業主が認定処分の取消訴訟等において、労災保険率の決定の基礎とされた労災保険給付の支給要件非該当性を主張するという手続保障の観点から、事業主に対して情報提供されることが適当と考える。
その際、被災労働者の個人情報の取扱いに留意しつつ、検討する必要がある。」
「メリット制適用事業場の事業主に対して提供する労災保険率の決定の基礎となった保険給付に関する情報については、事業主が保険料の認定処分の取消訴訟等において、労災保険率の決定の基礎とされた労災保険給付の支給要件非該当性を主張するという手続保障の観点から、事業主に対して提供され、事業主が自ら負担する保険料が何故増減したのかがわかる情報を知り得る仕組みが設けられることが適当と考える。
その際、提供する情報の範囲については、保険給付に関する情報には被災労働者に係る機微な情報を含み得ることに留意しつつ、検討する必要がある。」
まさに労災防止努力よりも労災保険給付請求を行う労働者を攻撃するような悪質な企業こそが、労働基準監督署や被災労働者に対する圧力・攻撃を行い、また、労災認定を争っているという現実に照らして、少なくともメリット制が廃止されない限り、悪質な事業主が被災労働者に対する圧力・攻撃に悪用する可能性が容易に想定される、事業主への情報提供を制度化することには反対である。
そもそも労災保険制度は、労災被災者の迅速かつ公正な保護こそが目的であるのに、今回の研究会の議論でも中間報告書でも、その視点がおざなりとなっている。そして、事業主による労災保険給付の支給要件非該当性を主張する手続保障の観点ばかりが考慮されている。
研究会の議論でも、委員から、「今後、増加していく可能性のある不服申立てや、それに向けて使用者が様々なアクションを起こすことで、被災労働者や関係者に事実上生じ得る直接・間接の負担について、どのように考えるか」「私自身は労災認定の実務等に関与しておりませんので、正確な知見を持ちません」(第5回議事録)などという指摘も出ている。つまり、情報提供によってどのような悪影響が労災被災者にもたらされるのかについて、現場の実態を丁寧に確認・検討しないままに、情報提供の議論を先行させているのであり、きわめて無責任な議論である。過去には、労働基準監督署が、症状固定と労災給付打ち切りの決定を事業主に通知したために、事業主が被災労働者に強引な復職要求を突きつけ、問題となった事案もある(2014年、京都労働局管内の事案)。
現行どおり、「個人情報なので請求人本人に尋ねてください」という対応で問題ないと考える。
3.遅発性疾病に係る保険給付の給付基礎日額
中間報告書は、次のように結論づける。
ケース1:有害業務に従事した最終の事業場を退職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合については、「労災保険の社会保障的性格や生活保障の観点から、発症時賃金を原則とし、発症時賃金が、ばく露時賃金より低くなる場合は、例外的にばく露時賃金を用いることが適当であるとの意見が大宗を占めたところであるが、その後の働き方の違い等で給付基礎日額の扱いが異なるのは公平ではないという少数意見があったことにも留意が必要である。」
ケース2:有害業務に従事した事業場を退職した後、就業していない期間に発症した場合については、「労災保険法が想定していないケースとも考えられるという少数意見もあったが、労災保険法が使用者の災害補償責任を担保していることを踏まえれば、当面は現状を維持することが適当と考える。一方、今後、各種給付の制度趣旨を検討することとあわせて、本ケースにおける給付の在り方について再度検証することが望ましい。」
以上の論点については、労働者が、疾病の発生のおそれのある作業[有害業務]に従事した事業場で、最終ばく露後も、当該有害業務以外の業務に従事して働き続けて在職中に発症した場合(①)または退職後に発症した場合(②)には、同一事業場における発症時賃金(①)または退職時時賃金(②)を用いることとの比較で考えるとわかりやすい。
ケース1の場合の結論は、同一事業場で働き続けた場合と同様に、在職時賃金を用いることを原則とするという「大宗の意見」に賛成である。
ケース2の場合についても、同一事業場で働き続けた場合と同様に、有害業務以外の業務に従事した別の事業場における退職時賃金を用いることを原則とするよう要望する。
ケース1の場合について、「大宗の意見」とともに「少数意見があったことにも留意が必要」としたのは、最終判断を労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の判断に委ねるという趣旨かとも思われるが、ケース1及び2ともに、上記のように同一事業場で働き続けた場合と同様の取り扱いにする改正を要望する。
4.遺族(補償)等年金
中間報告書は、次のように結論づける。
「遺族(補償)等年金の在り方を考えるにあたっては、本来、制度の趣旨を踏まえることが前提であるが、…本研究会においては遺族(補償)等年金の制度趣旨に関して一致した見解を得るには至らなかった。
しかし、…そのいずれの考え方を採ったとしても、給付の要件に関して、遺族(補償)等年金における夫と妻との支給要件の差を設ける合理的理由を見出すことは困難であり、夫と妻の要件の差については解消することが適当と考える。
また、その具体的な解消方法については、夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当であるとの意見が大宗を占めた。なお、妻の支給要件を夫に合わせることも検討すべきという少数意見があったことに留意が必要である。
将来的には、既に述べた遺族(補償)等年金の制度趣旨を踏まえた議論を行い、夫と妻以外の者に対する支給要件を含めた年金の支給対象者の範囲や給付期間の妥当性を含め、遺族(補償)等年金の制度全体の在り方について、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある。」
「夫と妻の要件の差については解消することが適当」とする結論に賛成するとともに、「その具体的な解消方法については、夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当である」とする「大宗の意見」に沿った改正を要望する。「妻の支給要件を夫に合わせることも検討すべき」という少数意見に留意する必要はなく、むしろ、同性パートナーで、自治体や会社で認めていない場合でも給付対象となるようにするべきである。
中間報告書は続けて、次のように結論づける。
「遺族(補償)等年金の制度趣旨をどのように解するのかという点はあるが、給付の期間については、現行の長期給付を維持することが現時点では適当であると考える。ただし、中長期的には、公正な保護の検討に当たって有期給付化についても考慮要素の一つになりうるという少数意見があったことに留意が必要である。」
「特別加算の取扱いについては、昭和45年の創設時の考え方は現代では妥当しないという意見で一致したものの、特別加算による夫と妻の差の解消の具体的な方策については、対象範囲を配偶者以外にも広げるのか、障害を持つ遺族に加算することの意義をどう考えるのか、さらには年金本体給付の水準との関係をどう考えるのか、など将来の受給者に広い影響を与える事項であることから、労使を含めて更に議論を深める必要がある。」
「現行の長期給付を維持することが現時点では適当」とする結論についても賛成である。
労災保険給付の水準全般を改善(引き上げ)すべきであるという観点から、遺族数が1人の場合の年金額を、現行の特別加算を加えた給付基礎日額の175日分に引き上げるとともに、遺族数が2人、3人、4人以上の場合についても引き上げることによって、特別加算を解消することを要望する。
なお、中間報告書は、次のようにも言う。
「遺族(補償)等年金の制度の趣旨・目的については、制度創設当初に謳われた『被扶養利益の喪失の填補』という概念に今日でも意義を見出せるという意見があった一方、遺族が自立するまでの期間を支える生活保障としての意義、労働者の死亡によってもたらされる永久的全部不能を補うものといった意見などの多角的な意見が示されたものの、遺族(補償)等年金の今日における趣旨・目的について、研究会として意見の一致には至らなかったことから、引き続き、専門的見地から議論を行う必要がある。」
「生計維持要件については、上記のとおり、現在の要件やその運用を是認し得るとの意見と、現在の生計維持要件の運用について検証が必要との意見があり、喫緊の見直しをすることは要しないものの、家族や家計維持の在り方が多様化していることを踏まえれば、遺族(補償)等年金の制度趣旨の検討と合わせて、引き続き、専門的見地から議論を行う必要がある。」
「今後、遺族(補償)等年金の制度趣旨を検証していく中で、労働基準法の遺族補償との関係についても、あわせて検討することが望ましい論点であり、引き続き、専門的見地から議論を行うことが必要である。」
これらの論点については、今後の議論をみながら必要な意見を表明していきたいと考えているが、例えば、全国脊髄損傷者連合会が、少なくとも障害等級または傷病等級が1級または2級の者については、厳密に業務起因性の立証を必要とせずに、原則として遺族(補償)給付の対象とする改正等を求め、全国じん肺患者同盟も遺族(補償)給付の取り扱いの見直しを求めていることも指摘しておきたい。
また、労働基準法の遺族補償との関係で「労災保険給付を受ける労働者と労働基準法第81条の打切補償との関係を議論すべきとの意見があった」とされているが、われわれはすでに、労働基準法第81条と労災保険法第19条をともに廃止するよう要望している。
5.災害補償請求権、労災保険給付請求権に係る消滅時効
中間報告書は、次のように結論づける。
「消滅時効期間の在り方に関しては、(2)~(4)までの論点について検討をしてきたが、いずれも委員の意見が分かれ、統一的な結論を得るには至らなかった。
消滅時効期間の在り方については、被災労働者の保護の観点から、これらの意見も踏まえて、労使を含めて更に議論を深める必要がある。」
検討された論点は、(2)現行の時効期間に見直しは必要か、(3)何らかの手当を行う場合に考え得る方法について、(4)他の社会保険と異なる労災保険特有の事情があると考えられるか、である。
消滅時効期間については、まず早急に、民法による原則の改正(平成29年)に伴って、労働基準法による賃金請求権の消滅時効期間について従前2年間であったものを5年間に改正されたこと(令和2年、ただし当分の間3年間)と同様に、災害補償請求権、労災保険給付請求権に係る消滅時効についても5年間とすることを原則とする改正を行い、ただちに施行するよう要望する。
合わせて、精神障害に関する特別の取り扱いも議論されたようだが、石綿関連疾患に関する取り扱いについて検討されるべきである。石綿関連疾患については、時効により受給権が消滅した事例についても救済が必要であるということから、平成18年の石綿健康被害救済法(厚生労働省所管分)によって特別遺族弔慰金・特別葬祭料の制度が創設された。当初は、同法施行以前に時効が成立した事例に限定した、3年間の時限立法であったが、平成20年、平成23年及び令和4年と三度の法改正が行われてきた。改正によって、同法施行後に時効が成立した事例も対象とされたばかりでなく、改正法施行時点でまだ時効が成立していない事例も対象に追加され拡大されながら、請求期限の延長が重ねられている。現在では、令和8年3月27日までに死亡し時効が成立した事例が対象で、請求期限は令和14(2032)年3月27日までとなっている。
本来であれば、これは労災保険法の改正によって対処すべき課題である。石綿関連疾患をはじめとした一定の職業病等については、上記の原則とは別に、消滅時効期間を廃止することを含めた改正を早急に検討すべきである。なお、この改正が実現すれば、石綿健康被害救済法(厚生労働省所管分)は不要になるかもしれず、そうすると現行の労災保険給付の給付基礎日額算定では労災保険の遺族(補償)給付が特別遺族弔慰金よりも低額となる場合に選択の余地がなくなるという不利益が生じる可能性はあるがやむを得ないものと考える。
なお、休業最初の3日間(いわゆる「待期期間」)について、労働基準法上の災害補償請求権との関連で言及があるものの、労災保険の休業(補償)給付の対象に追加することについて、見解が示されていないが、強く改正を要望する。
6.社会復帰促進等事業
中間報告書は、次のように結論づける。
「社復事業として実施される労働者やその家族に対する給付については、従来は処分性が認められなかった特別支給金も含めて処分性を認め、審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当と考える。」
「特別支給金については、その果たしている機能や保険給付と一体として支給されている実態等を踏まえれば、これを保険給付として位置づけることにより補償の安定性を確保することに資すると考えられるが、これを保険給付として位置づけることで民事上の損害賠償の調整対象となり労働者側に不利となり得ることや、ボーナス特別支給金の算定が難しい等、保険給付化を行う際の具体的な課題も多いことから、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある。」
「労働者等に対する給付的な社復事業に対する不服申立てについては、国民のわかりやすさや利便性の観点から、保険給付と同様に労審法の対象とすることが適当と考える。」
最初及び最後の結論について賛成であり、結論の内容に沿った改正を要望する。
われわれはすでに、「休業特別支給金を給付に組み入れることを含めて、給付水準を100%に引き上げること」を要望している。この場合、休業(補償)給付を80%に引き上げれば、休業特別支給金と合わせて100%を達成できるうえに、後者はなお民事上の損害賠償の調整対象とはならないので労働者側に有利になり得るという意見があるかもしれないが、われわれはそのような立場はとらない。むしろ、休業特別支給金を組み入れた休業(補償)給付を120%に引き上げるべきかどうかという議論をすべきであろう。
7.労働基準法上の「労働者」以外の者への労災保険法の適用(適用関係総論)
中間報告書は、次のように結論づける。
「現状においては、労災保険法の強制適用の範囲を労働基準法が適用される労働者以外の就業者にも拡大することについては、なお、多くの議論の余地がある。労災保険法の強制適用の範囲については、労働基準法上の「労働者」に関する概念の議論も踏まえつつ、労働基準法との関係も含めた労災保険制度の位置づけと保険料負担の在り方も含め、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある。」
プラットフォーム労働者に対するプラットフォームを含め、労働安全衛生リスクを管理し得る立場にある者に一定の責任を負わせるという観点も含めながら、労働基準法、労災保険法、労働安全衛生法の適用対象を拡大する議論の促進を要望する。
8.家事使用人への災害補償責任及び労災保険法等の適用
中間報告書は、次のように結論づける。
「家事使用人の保護を巡っては、家事使用人に対する補償の必要性は高い。家事使用人への労働基準法の適用については、労働政策審議会労働条件分科会で別途議論がなされているところであるが、仮に労働基準法が家事使用人に適用される場合には、使用者である私家庭の私人は同法に定める災害補償責任も負うことが適当であり、労災保険法を強制適用することが適当と考える。
その際、労災保険法や徴収法を私家庭の私人に適用するに当たっては、履行確保の可能性、また私家庭の私人が負う保険関係の手続に係る事務負担の軽減も含めて、運用上の課題を検討することが必要である。」
「労災保険法を強制適用することが適当」とする結論について賛成であり、労働基準法の適用及び労災保険法の強制適用を実施する法改正を要望する。
9.暫定任意適用事業
中間報告書は、次のように結論づける。
「暫定任意適用事業については、労働実態を把握する手段も多様化していると考えられることや既に労災保険に加入している暫定任意適用事業をみても、重大事故が散見され、保護の必要性が高まっているといえることを踏まえれば、農林水産省とも連携の上、順次、強制適用に向けた検討を進めることが適当と考える。
ただし、その際、農林水産事業者の理解に加え、これまで適用上の課題とされてきた事業者の把握や、保険料の徴収上の課題がどの程度解決されつつあるのかの具体的な検証が必要であり、また、零細な事業主の事務負担の軽減等も十分に配慮する必要がある。この点、例えば、事業主と関係団体等との連携や協力の在り方等についての検討も含め、その実現可能性や実効性についても農林水産省の協力も得つつ、検討することが必要である。また、林業及び水産業についても農業と同様、課題の解決策を検証した上で検討を進める必要がある。」
われわれはすでに、「暫定任意適用事業を廃止する」ことを要望しており、速やかな改正を要望する。
10.特別加入制度
中間報告書は、次のように結論づける。
「特別加入団体が災害防止の取組を担うことができるのか、また、それを義務付けるべきかとの点については、本研究会において複数の意見が見られた。
既に特定フリーランス事業に係る特別加入団体については、災害防止のための教育の結果を厚生労働省に報告するとの要件が追加され、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会においても、委員より、他の団体にも同様の要件を課すことについて意見が示されている。今後、労使を含めて更に議論を深める必要がある。」
「特別加入団体の承認や取消しの要件については、特別加入団体の性質を明らかにする上でも法令上に明記しておくことが適当と考える。
その際、承認の取消し(保険関係の消滅)に直結することは特別加入者に対して大きな影響をもたらすことから、承認の取消し等に先だって、改善を要求する等、段階的な手続を設けることが必要である。また、仮に、特別加入団体に災害防止措置に関わる役割や要件を求めるのであれば、法令的根拠を設けることが必要である。」
「特別加入団体の承認や取消しの要件を法令上に明記しておくことが適当」とする結論に賛成であり、また、災害防止に関して、少なくとも特定フリーランス事業に係る特別加入団体に課せられているものと同様の要件について課すよう、速やかな改正を要望する。
また、特別加入の対象範囲の拡大が、労災保険法の強制適用範囲の拡大に向けた議論の進展を妨げないようにする配慮も必要と考える。
11.その他
われわれは、すでにふれた「待期期間中の休業(補償)給付」、「打切補償規定」のほかにも、「傷病補償年金」、「介護補償給付」、「遺族補償給付」、「通期災害保護制度」、「不服審査制度」、「最低・最高限度額」、「解雇制限」等々についても要望を行っており、検証・議論が行われることを要望する。
昭和63年の労働基準法研究会(災害補償関係)も「中間報告」どまりで、当時のメンバー(西村健一郎助教授、当時)の「不十分なのでもう一度議論するべきだ」という進言を、労働省(当時)が無視して今日に至っている。当時も問題となったが、一度も被災者と会ったこともない法律研究者だけが議論するのではなくて、被災者や災害防止団体、医療関係者なども参加する、公開の検証・議論の場を設置するべきである。
2025年8月5日
全国労働安全衛生センター連絡会議
安全センター情報2025年10月号