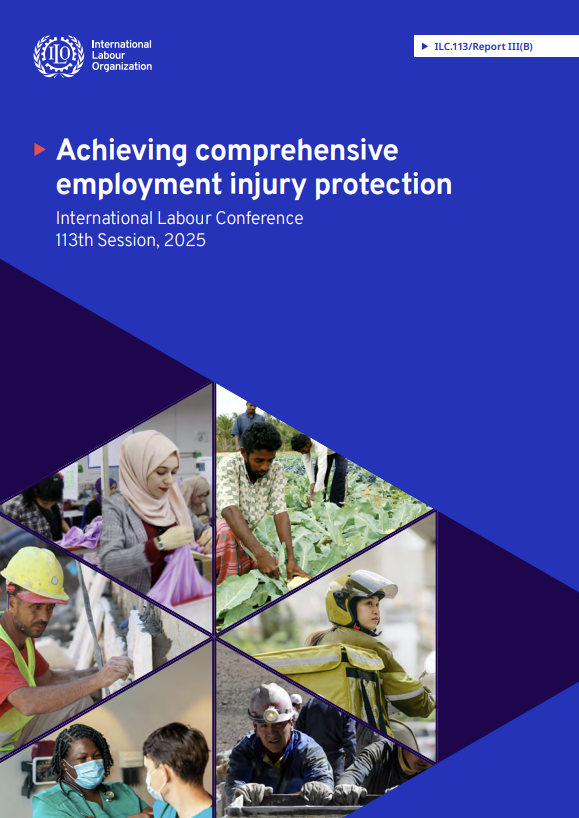特集/労災補償制度の課題/包括的な労働災害保護の実現-ILO委員会の勧告内容-第113回ILO総会報告書から
6月に開催される第113回国際労働会議の第3議題「条約及び勧告の適用に関する情報及び報告」のための、条約及び勧告の適用に関する専門家委員会の報告書(ILC.113/Report III(B))「包括的な労働災害保護の実現」が2025年2月28日に公表されている。労災補償(「employment injury protection」という言葉を使っているが「労働災害保護」と訳した)に関連した以下の6つの文書を一括レビューした初めての一般調査報告書である。
・ 1921年労働者補償(農業)条約(第12号)
・ 1925年均等待遇(災害補償)条約(第19号)
・ 1925年均等待遇(災害補償)勧告(第25号)
・ 1964年労働災害給付条約[付表1980年改正](第121条)
・ 1964年労働災害給付勧告(第121条)
わが国の労災補償制度のあり方を考えるうえでも貴重な情報であり、200頁を超える報告書だが、委員会の勧告内容と考えられる、太字のイタリック体で表記された個所のみ全文を仮訳して紹介する。
目次
第1部 労働災害保護に関連した原則、事故及び対象
第1章 労働災害保護の目標、目的及び主要な特徴
▶1.1. ILOの労働災害保護に対する規制アプローチの進化
▶1.2. 労働災害保護制度の概要
加盟国における労働災害保護制度の多様性を認識しつつも、委員会は、そのような制度は、労働者の強制的な加入、健全な財政基盤及び適切な管理を基盤とし、労働者または使用者の側の過失の有無にかかわりなく、包括的な範囲の労働災害給付の提供を確保するものであるべきことを強調する。委員会は、使用者が労働災害給付を直接提供する責任を負ってはならないことを想起する。委員会は、労働災害給付を適時に提供し、少なくとも条約第102号(第Ⅳ部)及び/または条約第121号で規定された保護の最低水準で達成することの重要性を強調する。
[前略] 委員会は、使用者が労働災害保険に加入しない場合または保険料を支払わない場合であっても、労働災害給付は、少なくとも第102号または第121号条約で確立された水準で提供されるべきであることを強調する。
▶1.3 包括的な労働災害保護に向けて
66. 委員会は、労働災害の防止に向けた統合的アプローチの重要性を強調し、これには適切な現金給付及び医療給付、医療的及び職業的リハビリテーションサービス、並びに職場における労働安全衛生措置が含まれるべきである。委員会は、この点において、労働安全衛生、労働環境、雇用及び職業リハビリテーションに関する一貫した国の政策の設定及び実施が、労働者を労働災害から効果的に保護し、その長期的な影響を軽減するために最重要であることを強調する。
第2章 労働災害事故
▶2.1. 労働災害の定義及び種類
2.1.1. 労働関連災害
79. 委員会は、多数の加盟国が、第121号条約第7条(1)並びに第121号勧告段落5(a)及び(b)に沿って、労働関連災害の広範な定義を確立していることを歓迎する。委員会は加盟国に対して、労働災害給付を提供する目的のために、労働関連災害の定義を拡大して通勤災害を業務上災害に含めるよう強く奨励する。委員会はさらに加盟国に対して、通勤災害が労働災害制度以外の社会保障制度の対象とされている場合には、提供される給付が、まとめると、条約121号第7条(2)にしたがって、少なくとも同条約で求められているものと同等であることを確保するよう強く奨励する。
2.1.2. 職業病
89. 委員会は加盟国に対して、第121号条約別表Ⅰに掲げられた職業病が、国の法令によって職業病とみなされることを確保するよう強く奨励する。委員会はさらに加盟国に対して、同別表に掲げられた疾病について、法律及び慣行上、職業起因性の推定の原則を適用するよう奨励する。この点において、委員会は、保護対象者が、国のリストによって対象とされてはいないが第121号条約別表Ⅰに掲げられている疾病の、職業起因性の立証責任を負わないことを想起する。
職業病リストの更新
95. 委員会は加盟国に対して、科学的根拠及び進展、並びに技術的進歩に基づいて、国の職業病リストを定期的に更新することを奨励する。委員会は加盟国に対して、国の職業病リストを更新する際には、第194号勧告(2010年改訂)で確立された職業病リストを、これに関する最新のILO基準として考慮するよう勧める。委員会は、定期的な国の職業病リストの改訂に関連する意思決定プロセスにおける、社会パートナーの参加の重要性を強調する。
心理社会的リスク及び精神障害
99. 委員会は加盟国に対して、国の職業病リストに精神障害を含めることによって、労働災害保護を精神障害に拡大する努力を継続するよう奨励する。委員会は、とりわけ労働者がそのような慣行にもっとも脆弱な部門において、職場暴力及びハラスメントを防止するとともに、心理的及び身体的傷害につながるそのような暴力及びハラスメントの事例に医療及び現金給付を提供する必要性に、加盟国の注意を喚起する。
▶2.2. 事故の種類
2.2.1. 負傷または疾病
2.2.2. 一時的または初期労働不能
2.2.3. 全部または一部永久的労働不能
2.2.4. 労働者の死亡に起因する扶養の喪失
112. 委員会は、国の労働災害保護制度が、第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約で概述される4つの事故、すなわち、(a)負傷または疾病、(b)負傷または疾病に起因する一時的または初期労働不能及び関連する稼得の停止、(c)永久的である可能性のある稼得能力の全部または一部喪失若しくは相当する機能の喪失、並びに(d)扶養者の死亡に起因する扶養の喪失、を包含することを確保することの重要性を強調する。
第3章 個人の対象
▶3.1. 法的対象の概要
124. 労働者の健康、福祉、及び所得保障のための労働災害保護の重要性を認識して、委員会は加盟国に対して、第102号条約第33条及び第121号条約第4条に沿って、労働災害保護を、一時雇用、臨時、パートタイム、在宅及び家事労働者を含めすべての労働者、並びに、経済部門、職業及び雇用の性質により対象から除外されたままになっている可能性のあるあらゆる他の範疇の労働者にも、漸進的に拡大するよう強く奨励する。委員会は、特定の範疇の労働者を対象とする別の制度が、第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約で要求されるものと少なくとも同等である労働災害保護を提供することを確保する必要性を強調する。
▶3.2. 効果的な対象を確保するうえでの課題
129. 第102号及び第121号条約の目的が、最大数の労働者が労働災害保護を受けることを確保することであることを想起して、委員会は加盟国に対して、労働災害保護の対象におけるギャップを埋めるための努力を強化し、この点に関する権利及び資格の効果的な適用を確保するよう求める。委員会は加盟国に対して、管理手続の簡素化及び既存メカニズムを可能な限り特定の範疇の労働者に適合させることによって、労働災害給付へのアクセスを促進する措置を検討するよう要請する。委員会は加盟国に対して、効果的な労働災害保護対象を確保することを目的に、インフォーマル経済における企業及び個人の地位のフォーマル化、及びインフォーマル経済の労働者とその使用者の拠出型社会保障制度への包含を促進する努力を継続するよう求める。この点において、委員会はとりわけ、多くの国でインフォーマル雇用に従事する割合が高いことから、女性労働者について効果的な対象を確保することの重要性を想起する。
130. 委員会はさらに、労働災害保護によって対象とされ、適切に補償される労働者の数に関する統計データが不足していることを強調する。委員会はそれゆえ加盟国に対して、この点において、効果的に対象を評価し、対象におけるギャップの根本原因に対処するためのデータ収集を優先するよう奨励する。関連するデータは、可能な限り性別に分類されるべきである。
▶3.3. 農業労働者に対する適用の拡大
141. 委員会は、農業部門がもっとも危険な部門のひとつであり、高い労働災害率を伴うことを強調したい。この点において、委員会は加盟国に対して、少なくとも第102号(第Ⅳ部)または第121号条約のいずれかで規定された水準の労働災害保護によって、農業賃金労働者の法的及び効果的適用を確保するよう求める。委員会はさらに加盟国に対して、自営の農業労働者への適用を漸進的に拡大する努力を継続するよう奨励する。
▶3.4. 国民及び外国人に対する平等な取り扱い
152. 委員会は、外国人労働者が高い職業リスクを伴う可能性のある部門に従事することが多いことを想起する。在留資格の如何にかかわらず、外国人労働者とその扶養家族に、労働災害保護制度を拡大することは、所得保障、健康と福祉の確保、及び不平等と脆弱性の軽減に不可欠である。委員会は加盟国に対して、立法措置または多国間及び二国間協定のいずれかを通じて、第19号条約第1条、第102号条約第68条及び第121号条約第27条に沿って、所与の国で働く国民と外国人、及びその扶養家族に対して、労働災害保護に関して、待遇の平等を提供する措置を講じるよう求める。委員会はさらに、労働災害現金給付及び医療への効果的なアクセスを確保するために、外国人労働者が直面するあらゆる現実的障害に対処する必要性を強調する。
▶3.5. 様々な範疇の労働者の適用
3.5.1. 自営労働者
158. [前略] 委員会は加盟国に対して、自営労働者の社会保障制度への加入及び適用の拡大について、とりわけ可能な限り強制的社会保障制度の拡大を通じて、現金給付及び医療の両面に関して、解決策を追求することを検討するよう奨励する。
3.5.2. 家事労働者
164. 家事労働者がしばしば雇用において脆弱な範疇を構成している事実を考慮して、委員会は、他の労働者と平等な立場で、現金給付及び医療の双方に関して、労働災害保護について、家事労働者のための社会保障制度加入及び適用を増加させるための措置の重要性を想起する。委員会はさらに、法律で明示的に除外されていない場合であったとしても、労働時間または稼得の最低閾値が、現実に家事労働者を対象から除外する要因となっていることを想起する。委員会は、家事使用者が主に個人世帯であり、多くの家事労働者が複数の使用者のために働いていることから、可能な限り、管理手続の簡素化が、社会保護、とりわけ労働災害保護へのアクセスを促進する不可欠であることを強調する。
3.5.3. デジタルプラットフォーム雇用の労働者
169. 委員会は、デジタルプラットフォーム雇用の労働者に労働災害保護の適用を拡大するために加盟国によってとられている措置を歓迎するとともに、プラットフォーム労働者について労働災害保護へのアクセスを確保するその努力を継続するよう奨励する。この点において、委員会は、プラットフォーム労働者の雇用上または労働上の地位が明確に定められていないことが増加する労働者、とりわけ職業リスクに曝露している者、のための効果的な労働災害保護に課題を提示していることを強調する。
3.5.4. 船員及び漁業者
174. 委員会は、船員及び漁業者が、その労働及び雇用の性質のために特定の職業リスクに曝露しており、社会保障のこの部門への適用が他の部門よりもより問題であることを想起する。多くの国で、これらの2つの範疇の労働者に対する労働災害保護が、第121号条約で認められているように、主要な社会保障制度から分離されているが、委員会は、船員及び漁業者に対して分離された制度のもとで提供される労働災害給付が、2006年海事労働条約(MLC)及び第188号条約で定められた海上労働者に対して確立されたものと同等であることを確保する必要性を想起する。海事部門の国際的性質及び漁業部門における移住が、社会保障適用へのアクセスの保証に関して重大な課題を提起していることを想起して、委員会はさらに加盟国に対して、二国間及び多国間協定の締結を通じることを含め、船員及び漁業者に労働災害保護を拡大する努力を継続するよう奨励する。
第2部 給付及びその他の関連するサービス
第4章 医療及び関連する給付
▶4.1. 医療の性質及び対象範囲
179. 被災労働者の健康及びその労働能力並びに個人的ニーズに対応する能力を維持、回復及び改善するための医療の重要な役割を想起して、委員会は加盟国に対して、少なくとも第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約で規定された医療及び関連する給付を包含した包括的な医療措置を確保するよう強く奨励する。
4.1.1. 在宅訪問を含めた一般医及び専門医による入院及び外来治療
184. 委員会は、在宅訪問を含め、一般医及び専門医による入院及び外来治療によって提供される医療の重要な役割を強調するとともに、加盟国に対して、労働災害の被害者へのその提供を確保するよう奨励する。
4.1.2. 歯科医療
185. [前略] 委員会は、予防的及び治療的双方の歯科医療を提供することの重要性を強調して、加盟国に対して、労働災害の被害者へのその提供を確保するよう奨励する。
4.1.3. 自宅または病院若しくはその他の医療施設における看護
187. [前略]労働災害の被害者の健康及び回復のための看護の積極的な役割を認識して、委員会は加盟国に対して、看護が自宅、病院またはその他の医療施設において利用可能であることを確保するよう奨励する。
4.1.4. 病院、療養施設、サナトリウムまたはその他の医療施設におけるメンテナンス
189. [前略]病院及びその他の医療施設の医療サービスの提供における重要な役割を認識して、委員会は加盟国に対して、遠隔地及び孤立した地域を含め、医療施設の利用可能性を確保するよう奨励する。
4.1.5. 必要に応じて修理及び更新された、補綴物を含めた、歯科用、医薬品用及びその他の医療用または外科用補給品並びに眼鏡
194. 委員会は、歯科用、医薬品用及びその他の医療用または外科用資材からもたらされる重要な利益を認識して、加盟国に対して、必要に応じて、それらの品目の適時の修理または交換を含め、労働災害被害者に対してこれらの入手可能性を確保するよう奨励する。
4.1.6. 医療専門職に付随するものとして法的に認められたその他の専門職のメンバーにより、医師または歯科医師の監督のもとで提供されるケア
195. [前略]関連する医療ケアの補完的な性質の重要性を強調して、委員会は加盟国に対して、労働災害の場合におけるその提供を確保するよう奨励する。
4.1.7. 可能な限り労働の場所における治療
197. [前略] 被災労働者が緊急治療またはその他の何らかの即時医療措置を必要とする可能性があることを想起して、委員会は加盟国に対して、可能な限り、職場において適切かつ迅速な医療対応が利用できることを確保するよう奨励する。
4.1.8. 移送の提供
198. [前略] 委員会は、被災労働者の移送費用を対象とすることの重要性を強調する。これらの費用は、とりわけ遠方の病院またはリハビリテーションセンターへのアクセスが必要となる場合、また負傷が理由で公共交通機関の利用が困難な場合には、相当な負担となる可能性がある。
▶4.2. 医療の期間及び資格要件
203. 委員会は、医療は事故の全期間を通じて、すなわち、被災労働者の健康状態がそれを必要とする限り、第102号条約第38条及び第121号条約第9条(3)に沿って、提供されなければならないことを想起する。委員会は、医療措置の期間を制限することは、とりわけ長期疾病及び重傷の場合には、労働災害被害者に対して、その資源に比して不釣り合いで、回復の見込みを損なう費用を生み出す可能性があることを強調する。委員会はさらに、第102号条約第37条及び第121号条約第9条(2)に沿って、雇用期間、保険期間または保険料の支払い期間の長さなどの要因に基づく適格期間を、医療給付の資格要件として設定してはならないことを想起する。
▶4.3. 費用の分担
210. 医療給付についての自己負担金が、現実に医療へのアクセスに対する障害となる可能性があることを想起して、委員会は加盟国に対して、第102号及び第第121号条約で保障されている医療給付の全範囲を、事故の全期間について、労働災害被害者に無償で提供するよう強く奨励する。委員会は、医療費の対象について限度額を設定することは、事実上、医療措置の期間を制限する可能性があることを強調する。
▶4.4. 医療の組織
適切な質の医療の提供
218. [前略]この点において、委員会は、労働災害を負った農業労働者及び農村地域のその他の労働者に対して医療へのアクセスを確保することが、関係するすべての者に包括的かつ効果的な労働災害保護を保障するうえでとりわけ重要であることを強調する。
222. 委員会は、適切な質の医療の適時の提供が、被災労働者の健康及び労働能力並びに個人的ニーズに対応する能力を維持、回復または改善し、その労働能力を回復するという医療の目的を達成するために不可欠であることを強調したい。委員会はさらに、第102号条約第71条(3)及び第121号条約第25条のもとで、給付の適切な提供が国の一般的責任であることを想起する。この点において、委員会は、とりわけ農村地域及び遠隔地域において、医療労働者及び医療施設を十分な数、全国に均等に配置することの重要性、並びに資金不足に対処することの重要性を強調する。
第5章 労働災害現金給付
225. [前略]委員会は加盟国に対して、第102号条約第37条及び第121号条約第9条(3)にしたがって、労働災害給付の資格に適格期間を設定しないよう奨励する。
▶5.1. 一時的または初期労働不能の場合の現金給付
5.1.1. 待機期間及び支給期間
232. 委員会は、一時的または初期労働不能の場合における給付は、第102号条約第38条及び第121号条約第9条(3)に沿って、事故の全期間、すなわち稼得の停止を伴う負傷または疾病の状態にある全期間を通じて支給されなければならないことを想起する。とりわけ、病気ではあるが、障害年金の資格のない労働者に対して、法定の最大支給期間が終了した後であっても、一時的または初期労働不能に対する給付が継続して支給されることを確保することが必要である。委員会はまた加盟国に対して、一時的または初期労働不能の場合における給付を、いかなる待機期間なしに、または労働不能の最初の3日を超えない待機期間で、支給するよう奨励する。
5.1.2. 一時的労働不能の場合の給付水準
236. 委員会は、時間経過に応じて現金給付の水準を決定するうえで用いられる方法にかかわりなく、事故の全期間を通じて、条約で求められている最低給付水準を確保することの重要性を強調する。
239. 委員会は、稼得連動型給付の場合には、給付の算定のために考慮される給付の率または稼得についての最大限度が、第102号条約第65条(3)及び第121号条約第19条(3)の遵守を確保するやり方で決定されなければならないことを想起する。
242. 委員会は加盟国に対して、一時的または初期労働不能の場合における現金給付の率は、事故の全期間を通じて、少なくとも第102号(第Ⅵ部)及び第121号条約で求められている水準で設定されることを確保するよう奨励する。
▶5.2. 稼得能力の永久的全部または一部喪失若しくは相当する機能の喪失に関する現金給付(障害給付)
5.2.1. 障害の程度
249. 委員会は、障害給付の資格のための障害の最低程度は、第121号条約第14条(5)で求められているように、困難を回避するようなやり方で規定されなければならないことを想起する。委員会は、最低程度は軽度と定義される障害の程度よりも低い水準に設定されるべきであることを強調する。この点において、委員会は、軽度の障害であっても、被害者の生活の質及び雇用の機会に対して長期的な影響を及ぼす可能性があり、そのため適切な所得保障が必要あることを強調する。
250. [前略]委員会は、第102号及び第121号条約にしたがって、永久的労働不能の評価は、稼得能力の喪失及び/または機能の喪失にしたがって決定される可能性があることを想起する。委員会はさらに、障害を定義するために用いられる方法にかかわらず、給付は、軽度、中等度、及び全部障害について提供されなければならないことを想起する。さらに、中等度(軽度を超える)一部障害の場合に提供される給付は、全部障害に対する給付の適切な割合を占め、定期的に支払われなければならない。
5.2.2. 定期現金給付の水準
253. [前略]委員会は、給付率が保険期間または雇用期間に左右される場合には、給付率は、雇用初日に負傷した被保険者について、第102号条約(参照賃金の50%)または第121号条約(参照賃金の60%)で求められている代替率を達成しなければならないことを強調する。
以前の稼得の評価
259. 委員会は、稼得連動型障害年金の場合には、給付の算定のために考慮される給付の率または稼得についての最大限度が、第102号条約第65条(3)及び第121号条約第19条(3)の遵守を確保するようなやり方で決定されなければならないことをあらためて想起する。
給付の算定のために稼得が考慮される期間
262. [前略] 委員会は、労働災害給付の被害者に対する給付の算定のために、稼得が考慮されるもっとも適切な期間を選択できるようにする多様なアプローチを歓迎する。
永久的部分障害
サプリメント
5.2.3. 支給期間
268. [前略]この点において、委員会は、労働災害に関する障害給付が老齢年金に移行されている管轄区域においては、老齢年金の水準は、第102号または第121号条約で確立された労働災害給付の水準を下回ってはならないことを強調する。
272. 委員会は、第102号び第121号条約が、全部障害または中等度一部障害の期間全体を通じた、すなわちそのような障害が存在している期間を通じたまたは死亡までの、定期的支給の提供を求めていることを想起する。定期的支給という用語は通常、複数回に分けた一時金支給を含め一時金支給ではなく、「年金」(定期的長期給付)を指すことを想起して、委員会は加盟国に対して、労働災害に関する障害給付が時間的に制限されないことを確保するよう強く奨励する。委員会はさらに、労働災害に起因する障害を有する者が老齢年金を受ける資格を有する場合には、その者は少なくとも第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約で求められているものと同じ年金を受けるべきであるという事実を強調する。
定期的支給の一時金への換算
283. 委員会は加盟国に対して、第102号条約第36条(3)並びに第121号条約第14条(4)及び第15条(1)にしたがって、障害に関する労働災害給付は、例外的な状況、とりわけ障害の程度が軽度な場合、または権限を有する当局がそのような一時金いが被害者にとってとりわけ有利なやり方で利用されるだろうと考える理由がある場合、にのみ一時金支給として提供されることを確保するよう強く奨励する。委員会は加盟国に対して、一時金と定期的支給の間に公平な関係が保たれることを確保するよう奨励する。
5.2.4. 他者の継続的な援助または介護
291. 委員会は加盟国に対して、第121号条約第16条にしたがって、他者の継続的な援助または介護を必要とする障害を有する者に対して、定期的支給の増額若しくはその他の補足的または特別の給付の提供を確保するよう強く奨励する。委員会はさらに、そのような増額または給付を、他者の継続的な援助または介護の合理的な費用を賄うのに十分な水準で提供することの重要性を強調する。
▶5.3. 労働者が死亡した場合の現金給付(遺族給付)
5.3.1. 資格のある者
生存配偶者
301. 委員会は、第102号条約第Ⅳ部(労働災害による遺族給付)または第Ⅹ部(遺族給付)の受諾若しくは第121号条約の批准が、社会保護制度の進化の障害となることも、また概念的な家族モデルを改訂または既存の保護を削減する理由となることもないことを想起する。委員会はさらに、第102号及び第121号条約は最低要求事項を構成するものであり、加盟国はそれゆえ、例えば寡夫に対する追加給付を通じて、より良い保護を付与することができることを強調する。この点において、委員会は、遺族給付の資格をすべての生存配偶者及びパートナーに拡大するために加盟国によってとられている措置に正当に留意する。
子
309. 委員会は加盟国に対して、法的な婚姻関係または法的に認められた関係において出生したか否かにかかわりなく、死亡した労働者のすべての被扶養子が、第102号及び第121号条約双方の第1条(e)のもとでの子の定義に沿って、同等の条件で遺族給付の資格を有することを確保するよう奨励する。
その他の被扶養者
314. 委員会は加盟国に対して、第121号勧告段落13で示唆されているように、遺族給付に関連した対象を、両親、兄弟姉妹及び孫を含め、死亡者のその他の範疇の被扶養者に拡大し続けるよう奨励する。
5.3.2. 給付の水準
5.3.3. 支給期間
325. 委員会は、第102号及び第121号条約が、事故の全期間を通じた遺族給付の支給を求めていることを強調する。とりわけ、そのような期間の継続は、第102号条約第1条及び第121号で確立されているように、少なくとも死亡した労働者の子が一定の年齢に達するまでであるべきである。生存配偶者については、第102号条約第32条(d)で確立されているように、事故の期間は、自己扶養が不能であるという推定に基づくことができる。委員会はさらに、一時金支給は、第102号条約第36条(3)(b)に沿って、限定的な場合、とりわけ権限を有する当局が一時金が適切に利用されることを確認した場合、にのみ認められることを強調する。
5.3.4. 葬祭給付
331. 委員会は加盟国に対して、第121号条約第18条(2)で求められているように、葬祭の通常の費用が労働災害制度によって賄われることを確保するよう奨励する。委員会は、葬祭給付が適格期間の対象とされるべきでないことを強調する。
▶5.4. 定期的支給で遵守されるべき基準
336. 委員会は、 「熟練男性労働者」または「普通成人男性労働者」の賃金に対する参照は、すべての保護対象者に適用される現金給付の水準を設定するための算術的代理としてのみ用いられれることを想起する。委員会はさらに、この「性別偏向的な」統計的参照が、持続的な性別賃金格差を考慮して、男性労働者と女性労働者の双方に適用されるより高い保護水準を達成する効果を有することを想起する。[後略]
340. 委員会は、給付の代替率を計算するために適用されるパラメーターは、女性に対する差別を促進し、または特定の家族形態を支持することなく、加盟国が給付の適切性を確保するために達成すべきすべての現金給付の水準を設定するためのみに用いられるものであることを強調したい。委員会はまた、給付の代替率を計算するために設定されたパラメーターは、国レベルにおける特定の方法論を強制することではなく、現金給付が第102号及び第121号条約で確立された最低基準に沿っているかどうかを評価することであることを強調する。
第6章 労働災害の防止
344. 委員会は、予防的な労働安全衛生(OSH)文化を育成することの重要性を強調する。この点において、委員会は加盟国に対して、第121号条約第26条(1)(a)及び労働安全衛生に関する関連文書にしたがって、労働関連災害及び職業病の防止を目的として、保険及び社会保障制度とOSHに責任を有する当局との間の協力を強化する努力を継続するよう強く奨励する。
▶6.1. 労働安全衛生のための政策枠組み
▶6.2. 予防措置
6.2.1. インセンティブ
6.2.2. 予防防的医学検査
6.2.3. データ収集及び研究
6.2.4. 意識啓発
6.2.5. 教育及び訓練
364. 委員会は加盟国に対して、第121号条約第26条(1)(a)にしたがって、意識啓発活動、教育及び訓練、並びに調査及び研究を含め、労働関連災害及び職業病を防止するための多様な措置を採用するよう奨励する。委員会はさらに、労働関連健康障害の積極的な早期発見及び治療のために、初回及び定期的医学検査を含め、予防的健康サービスの重要性を強調する。
365. 委員会は、労働条件を改善するために、使用者に対して金銭的及び非金銭的なインセンティブを提供することの重要性を認識している。同時に、委員会は、それらのインセンティブを通じて受け取る利益が、正確な情報の報告に基づいていることを確保する必要性を強調する。委員会はさらに加盟国に対して、業務上災害及び疾病に関する正確かつ包括的な統計情報の収集及び編集の確保を継続するよう強く奨励する。
▶6.3. リスクの高い部門の労働者及び脆弱な状況にある労働者
373. 委員会は、特定の労働者グループにおける労働災害を防止するために一部の加盟国によって講じられている措置を歓迎する。安全で健康的な労働環境に対する権利を想起して、委員会は加盟国に対して、中小企業(SME)及び移住労働者を含め、リスクの高い部門の労働者及び脆弱な労働者について労働関連災害及び職業病の防止を確保するよう強く奨励する。
第7章 職業リハビリテーション及び障害者の雇用
377. 委員会は、職業リハビリテーションサービス及び雇用措置を含んだ政策を実施することが、障害の副作用を最小限にするとともに、労働災害保護制度の持続可能性に貢献することを想起する。委員会はさらに、労働災害に起因する障害を含め、障害を有する者の労働への復帰を支援する社会保護制度を確保するための政策が採用されるべきであることを想起する。
▶7.1. 職業リハビリテーションサービス
384. 委員会は加盟国に対して、第102号条約第35条及び第121号条約第26条(1)(b)に沿って、とりわけ遠隔地及び農村地域におけるものを含め、被災労働者のための職業リハビリテーションサービスへの効果的なアクセスを確保するよう強く奨励する。職業リハビリテーション措置の範囲及び種類は、障害を有する者が適切な雇用を確保、維持及び向上することができるようにし、それによりさらなる社会への統合または再統合を可能にすべきである。
7.1.1. リハビリテーション期間中の調整メカニズム及び現金給付の提供
388. 委員会は加盟国に対して、障害を有する者のリハビリテーションへの対処に向けた積極的なアプローチをとるために、一般リハビリテーションサービス、労働災害防止制度、保健及び医療サービス、並びに使用者との間の連携を強化するよう奨励する。この点において、委員会は、労働者が時期を早めて労働市場に戻る必要性を感じることなしに、リハビリテーションプロセスを完了できるようにするため、所得保障を確保する現金給付を維持することが不可欠であることを強調する。
▶7.2. 障害を有する者の雇用
398. 委員会は加盟国に対して、第121号条約第26条第1項(c)に沿って、労働市場及び社会への統合を促進することを目的に、障害を有する者に対して雇用サービスを提供するよう強く奨励する。委員会はさらに加盟国に対して、障害を有する者に対する雇用に関連した差別の防止及び根絶に関連したものを含め、この点に関する雇用政策及び戦略の設計及び実施に関する社会対話を強化するよう奨励する。
第3部 労働災害保護を可能にする法的、管理的及び金銭的セーフガード
第8章 労働災害保護制度の管理及び資金調達
▶8.1. 労働災害保護制度の管理
8.1.1. 概況
410. 委員会は加盟国に対して、労働災害保護制度の管理が透明性、説明責任、効率性及び公正性の原則に基づくことを確保することを目的とした措置を採用するよう奨励する。
[囲み] 委員会は加盟国に対して、利用可能な資源及び制度の財政的持続可能性を考慮しつつ、社会保障機関がデータを収集及び管理し、請求の処理及び調査を最適化し、並びに最終的に効率的な医療及び現金労働災害給付を提供する能力を向上させることを目的に、包括的で、相互に接続され、安全で透明性の高い情報システムに投資及び開発するよう奨励する。
8.1.2. 国の管理の特定の問題
民間または公的保険者の破綻
414. 第102号条約第71条(1)及び第121号条約第25条のもとで、国が労働災害保護の適切な提供に関する一般的責任を負うことを想起して、委員会は加盟国に対して、関連する保険者が破綻した場合には、医療及び現金労働災害給付への効果的なアクセスを確保するよう奨励する。委員会は加盟国に対して、権限の委譲の場合、または管理構造が分散化されている場合においても、一般的責任の原則を確保するよう奨励する。
強制加入及び保険料の徴収
423. 委員会は、第102号条約第71条(1)項及び第72条(2)並びに第121号条約第24条(1)及び第25条のもとで、国が労働災害給付の適切な提供及び関連する機関及びサービスの適切な管理に関する一般的責任を負うことを想起する。この点において、委員会は、機関及びサービスの機能不全により、裁判所への救済を求める必要が生じた場合には、その結果が労働災害の被害者及びその扶養家族に負わされてはならないことを強調する。
執行
428. 委員会は、公的及び民間保険機関が適切に機能することを確保するための、効果的な遵守及び執行メカニズムの重要な役割を強調する。監督及び監視システムは、違反の重大さに比例した十分な抑止力をもつ罰則と組み合わせて、法の適用及び義務の履行を確保するための重要なツールである。委員会は加盟国に対して、とりわけ被保険労働者の過少報告及び被保険稼得の過少報告がかかわる場合には、保険料逃れに対抗するための措置を講じるとともに、この点において十分に抑止力のある罰則を課すよう強く奨励する。
8.1.3. 参加型管理
436. 委員会は、労働災害保護制度の良好な運営及び適切な機能の確保並びに社会対話の促進のための、参加型管理の重要な役割を強調したい。さらに、社会パートナーは、受益者の特定のニーズ及び企業が直面する課題に関する知識に関してもっとも備えていることを想起する。委員会は加盟国に対して、第102号条約第72条(1)及び第121号条約第24条に沿って、保護対象者及び使用者の代表並びに公的当局が、管理に参加するか、若しくは公的当局によって規制される機関または立法機関に対して責任を負う政府部門に管理が委任されていない場合には、助言的な役割をもって参画することを確保するよう奨励する。
▶8.2. 労働災害給付の資金調達
446. 様々な資金調達方法を認識しつつも、委員会は加盟国に対して、第102号条約第71条(3)及び第121号条約第25条に沿って、現金及び現物による給付を適切に提供するために、労働災害保護制度の財政的持続可能性及び適切性を確保するよう強く奨励する。委員会は、給付の提供について個々の使用者の責任に基づいた労働災害制度を有する加盟国に対して、第102号条約第71条に定められた社会保険に基づく労働災害制度への移行を強く奨励する。委員会は、第102号条約第71条(3)で求められているように、労働災害度の財政的健全性を評価するために、定期的数理調査を実施することの重要性を想起する。
第9章 適正な給付の提供を確保する手続
▶9.1. 給付の申請及び請求の処理
448. [前略]委員会は、使用者が請求書の署名または国の請求手続におけるその他の要求事項の履行を怠った場合に、被災労働者またはその扶養家族が給付へのアクセスできることを確保する必要性を強調する。
453. 委員会は加盟国に対して、労働災害現金給付及び医療給付の請求手続が迅速で、アクセス可能かつ透明性のあるものであることを確保して、国籍及び職業にかかわりなく、すべての被災労働者とその家族が、その権利及び給付を適時かつ効率的なやり方で完全に行使できるようにするよう奨励する。委員会はさらに、被災労働者とその扶養家族が、なんらかの請求提出の遅延があった場合でも、とりわけ提出の遅延に合理的な理由がある場合には、給付を申請及び受給できることを確保する必要性を強調する。
▶9.2. 労働災害による障害の認定、評価及び見直し
461. 委員会は加盟国に対して、国の法令が、明確、透明性があり、公平で、アクセス可能であり、迅速に処理され、均一に適用される障害評価メカニズムを設定することを確保するよう奨励する。委員会は、障害の程度の適時の認定、評価、及び見直しの重要性を強調する。この点において、労働災害制度が、長期の潜伏期間を有する職業病の場合を含め、適切かつ適時の障害の確認並びに障害の程度の評価及び見直しを行うために、人員及び技術的設備を含め、十分な手段を有することを確保することが必要である。
▶9.3. 給付の停止
475. 委員会は、労働災害給付の全部または一部停止の根拠が、第102号条約第69条(a)から(g)及び(j)並びに第121号条約第22条(1)で特定された場合を超えてはならないことを強調する。委員会はまた加盟国に対して、給付の完全な累積が不可能である場合には、受益者が、少なくとも第102号条約第65条または第66条若しくは第121号条約第19条または第20条で定められた水準の給付を受給することを確保するよう奨励する。
▶9.4. 給付の調整
480. [前略] 委員会は、この点において、調整式にマクロ経済指標を含めているにもかかわらず、生活費に関連した給付の実際の価値が維持され、調整に関する関連統計データによって示されるべきであることを想起する。
482. [前略] 委員会は、この点において、第102号条約第65条(10)及び第66条(8)並びに第121号条約第21条(1)が加盟国に対して、給付の自動的物価連動を導入することを義務づけてはいないものの、そのような方法は、給付率をインフレ及び生活費に対して調整する点において、もっとも適切な方法である可能性があることを想起する。
484. 委員会は、第102号条約第65条(10)及び第66条(8)並びに第121号条約第21条(1)で求められているように、生活費の著しい変動に起因する一般稼得水準の著しい変動にしたがった給付の定期的見直しの重要性を強調したい。委員会は加盟国に対して、稼得能力の永久的喪失または機能の喪失に関する給付及び遺族給付を含め、長期労働災害給付の購買力を維持するよう強く奨励する。
▶9.5. 国外への給付の支給
491. [前略] この点において、委員会は、外国人労働者とその扶養家族が、国外での労働災害給付の提供に関して、国民と同等の待遇を受けなければならないことを強調する。[後略]
492. 委員会は、外国人労働者とその扶養家族が、国外での労働災害給付の提供に関して、国民と同等以上の待遇を受けべきであることを強調したい。とりわけ、平等な待遇の原則にしたがって、国外に居住する外国人労働者とその扶養家族は、第19号条約第1条に基づき、そのような給付が国民に提供される場合には、定期的現金給付及び医療を継続して受け続けられるべきである。委員会は加盟国に対して、第19号条約第4条に沿って、労働災害給付の移転可能性を確保するうえでの法的、行政的及び実務的な障害を克服または軽減するために、相互援助を提供するよう強く奨励する。
9.5.1. 多国間及び二国間協定並びに相互援助
500. 労働災害給付の移転可能性に関する多国間及び二国間社会保障協定締結の重要性を想起して、委員会は加盟国に対して、第19号条約第1条(2)に沿って、被災労者とその家族に対する国外での給付の支給を確保するために、そのような協定の締結及び有効な実施を強く奨励する。この点において、委員会は加盟国に対して、国の労働災害給付制度を管理する権限のある機関間の協力を強化するよう奨励する。
9.5.2. 給付金の支給を促進するための単独措置
503. 委員会は、対応する二国間または多国間社会保障協定が締結されていない加盟国に対して、国外への給付の直接支給を確保するよう奨励する。委員会はさらに、傷害が発生した国の領域内で彼らの給付に対する資格を提供及び維持するための手続を簡素化して、国外に居住する被災労働者の労働災害給付へのアクセスを促進する必要性を強調する。
▶9.6. 苦情及び不服申立手続
506. [前略]委員会は、第102号及び第121号条約は苦情を提出するための具体的な期間を設定してはいないものの、そのような期間は合理的な期間であるべきであることを想起する。
510.[前略] 委員会は、苦情または不服申立手続中の給付の支給を保証する立法規定を歓迎する。[後略]
513. 委員会は、国外に居住する被害者とその家族について苦情及び不服申立メカニズムへのアクセスを促進する必要性を強調する。[後略]
委員会は、第102号条約第70条(1)及び第121号条約第23条(1)で求められているように、効果的な苦情及び不服申立メカニズムへのアクセスを促進する必要性を強調したい。委員会は加盟国に対して、そのようなメカニズムが公正、アクセス可能、手頃な費用で、透明性があり、迅速であることを確保するよう強く奨励する。委員会はさらに、国外に居住する外国人労働者とその家族の司法へのアクセスを促進する必要性を強調する。
第4部 文書の潜在能力を引き出す
持続可能な開発のための労働災害保護
批准に関する見通し及び課題
労働災害給付の適切な提供を保証するための基準関連活動
技術的支援の提供
結 語
534. 委員会は、第12号、第19号、第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約、並びに第25号及び第121号勧告を一般調査の対象として選定した理事会の決定を歓迎する。これにより、委員会は、6つの文書を初めて一体として検討することができ、労働災害保護制度の開発に関するより一貫した見解を提供することが可能となった。この点において及び今後の取り組みにおいて、委員会は、労働の世界における女性及び男性の平等がILOの核心的な価値のひとつであり、ジェンダー平等がディーセントな労働の概念の不可欠な要素であることを想起する。委員会は、この一般調査が、それらの文書の範囲、可能性及び重要性並びにディーセントな労働の促進及び社会保護制度の強化における継続的な関連性に関する理解を深めることに貢献することを期待している。委員会はさらに、詳細な報告書様式への高い回答率を歓迎し、各国がこの取り組みを継続するよう奨励する。
535. [前略] 労働関連災害及び職業病の被害者とその扶養家族に対する適切かつ包括的な保護の重要性を想起して、委員会は加盟国に対して、公正かつ適時の包括的な労働災害給付の提供を可能にする、社会保険、労働者の強制加入、財源の共有とリスクの分担による健全な資金調達、また適切な管理に基づいた労働災害保護制度を確立及び維持するよう強く奨励する。委員会はさらに加盟国に対して、直接給付を提供する使用者の責任に基づいた使用者責任メカニズムから、第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約に沿った労働災害保険制度への移行を確保するよう奨励する。
536. [前略]委員会は加盟国に対して、第121号条約第7条及び第8条並びに第121号勧告第5項、第6項及び第7項に規定にしたがって、労働関連災害び職業病の場合における労働災害給付を提供する努力を継続するよう奨励する。とりわけ、委員会は加盟国に対して、第121号条約第7条第2項及び第121号勧告第5項(c)に沿って、労働災害給付を提供する目的のために、通勤災害を含むように労働災害の定義を拡大するよう奨励する。委員会はさらに加盟国に対して、国の法令が、少なくとも条約第121号別表Ⅰに掲げる職業病を対象とすることを確保するよう奨励する。加えて、委員会は、科学的証拠及び進歩、技術的発展にしたがい、社会パートナーの参加のもとに、国の職業病リストの定期的更新を実施することの重要性を強調する。
537. [前略] 委員会は、第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約が、それらの制度及びメカニズムが条約の規定に沿っている限り、上述した労働災害事故を対象とし、対応する給付を提供する様々な制度及びメカニズムを認めていることを想起する。4つのすべての事故について、第102号(第Ⅳ部)または第121号条約で確立された最低パラメーターを満たす労働災害医療給付及び現金給付の資格が確立されるよう確保することが必要である。
538. [前略] 委員会は、労働災害保護における法的及び実効的側面の双方における対象範囲のギャップを埋めるための緊急の必要性を強調したい。この点において、委員会は加盟国に対して、第121号条約第4条(1)に沿って、公的部門及び共同組合を含めた民間部門における、実習生を含めたすべての労働者とその家族に対し、労働災害保護を漸進的に拡大する努力を追求するよう強く奨励する。さらに、可能な限り、労働災害に対する適用は、第121号勧告段落3に規定されているように、自営業者を含め一定の範疇の人々に提供されるべきである。ディーセントな労働条件を確保する目的のために、委員会はさらに加盟国に対して、とりわけ管理手続の簡素化、遵守及び執行メカニズムの強化、必要に応じてインフォーマル経済からフォーマル経済への移行に対処することによって、効果的な労働災害保護の適用において直面する課題に対処するための措置を講じるよう奨励する。
539. [前略] 農業労働者の法的及び効果的な適用に課題が残っていることを踏まえて、委員会は加盟国に対して、それらの適用を農業労働者に拡大することを目的に、第12号条約第1条に規定されているように、国の法令における労働災害給付に関する規定をすべての農業賃金稼得者に拡大するための措置を講じることを検討するよう強く奨励する。委員会はさらに、[国際労働]機関及びその三者構成員に対して、第102号(第Ⅳ部)及び/または第121号条約の効果的な実施に向けて協調した措置を講じるよう求めた理事会関の決定を想起する。
540. [前略] 委員会は加盟国に対して、第19号条約第1条、第102号条約第68条、及び第121号条約第27条に沿って、労働災害給付へのアクセスに関して、所与の国で働く国民と外国人、及びそれらの扶養家族の間における待遇の平等を確保するよう強く奨励する。委員会はさらに、第19号条約第1条第2項にしたがって、居住の状況にかかわりなく、外国人労働者とその家族に待遇の平等が保障されるべきであることを強調する。
541. [前略]委員会は、第19号条約第1条(2)に沿って、給付の移転可能性を確保するために、とりわけ多国間及び二国間社会保障協定の締結を通じて、協力を強化することの重要性を強調したい。この目的のために、平等な取り扱い原則び労働災害給付の適切な提供を効果的に確保するために、法的、管理的、実務的な障害を克服する必要がある。
542. [前略]委員会は加盟国に対して、第102号条約第34条(2)及び第121号条約第10条(1)で規定されているように、適切な質の医療及び関連する給付が、事故[の全期間]を通じて、すなわち被災労働者の健康状態がそれを必要とする限り、いかなる適格期間もなしに、かつ適時に提供されることを確保する強く奨励する。委員会はさらに加盟国に対して、医療給付の全範囲を、第102号条約第34条(2)及び第121号条約第10条(1)に規定されているように、労働災害の被害者に無償で、事故の期間全体について提供するよう奨励する。
543. [前略]
▶[前略] この点において、委員会は、被災労働者が労働不能である限り、そのような給付が支給されることを確保する必要性を強調する。
▶[前略] 委員会はそれゆえ加盟国に対して、現金給付の資格を開始するために、いかなる待機期間もなしに、または待機期間が労働不能の最初の3日を超えないことを確保するよう奨励する。
544. [前略]
▶[前略]委員会はそれゆえ加盟国に対して、第102号条約第36条(3)及び第121号条約第15条で求められているように、一時金支給は例外的な場合、とりわけ障害の程度が軽度な場合、または権限を有する当局がそのような一時金が被害者にとってとくに有利なやり方で使用されると考える理由がある場合、のみに限って認めるられることを確保するよう強く奨励する。[後略]
▶[前略]委員会は、他者の継続的な援助または介護により生じる合理的な費用を賄うために、そのような増額または給付を十分な水準で提供することの重要性を強調する。
545. [前略]
▶[前略]給付は、事故を通じて、すなわち労働者の死亡に起因する支援の喪失期間全体にわたって提供されるべきである。
▶[前略]委員会は加盟国に対して、第121号条約第18条(2)に沿って、葬祭給付は、葬祭の通常の費用を下回ってはならない、定められた率で提供されることを確保するよう奨励する。。
546. [前略] 委員会は、加盟国に対して、事故の全期間を通じて、かついかなる適格期間もなしに、労働災害現金給付の率が、少なくとも第102号(第Ⅵ部)及び第121号条約で定められた水準以上であることを確保し続けるよう奨励する。
547. [前略] 委員会は、第102号条約第65条(10)及び第66条(8)並びに第121号条約第21条に規定されているように、それが生活費の著しい上昇に起因する場合には、稼得の一般水準の著しい変化により、現在の経済状況と一致しなくなった定期的支給の率を見直すことの重要性を強調する。委員会は加盟国に対して、給付の自動的な物価連動を通じてのものを含め、長期労働災害給付、とりわけ障害給付及び遺族給付金、の購買力を維持し続けることを奨励する。
548. [前略]委員会は、労働災害保護制度の管理における社会パートナーの参加が、適切なガバナンス及び情報に基づいた意思決定に貢献するとともに、公衆の信頼を維持及び強化することができることを想起する。
549. [前略] 委員会は加盟国に対して、社会保障機関がデータを収集及び管理する能力を向上させることを目的に、包括的かつ相互接続され、安全で透明性の高い情報システムへの投資及び開発するよう奨励する。これは、制度の財政的持続可能性を考慮しつつ、使用者と労働者の登録及び保険料の徴収、請求の処理及び調査の最適化、可能な限り、効率的な医療及び現金給付の促進につながるだろう。さらに、情報システムの開発は、多様な関係者の協力を促進し、ベストプラクティス、技術及び能力構築イニシアティブの共有を可能にする可能性がある。
550. [前略] 委員会は、労働災害制度を管理する公的及び民間機関の適切な機能及び給付の適切な提供についての責任は、国にのみ帰属することを強調する。委員会はさらに、公的または民間機関の機能の不備または使用者がその義務の遵守を怠ることによる結果を、労働災害被害者またはその家族に負担させてはならないことを強調する。
551. [前略]委員会は加盟国に対して、第102号または第121号条約で求められている水準で医療給付及び現金給付を適切に提供するために、労働災害保護制度の財政的持続可能性を確保するよう強く奨励する。委員会は、労働災害制度の財政的健全性を評価するために、定期的数理調査を実施することの重要性を想起する。また、使用者が労働災害給付の提供について直接責任を負うべきではないことを強調する。
552. [前略] 委員会は加盟国に対して、国籍及び職業にかかわりなく、すべての被災労働者とその家族がその権利及び資格を完全に行使できるようにするために、労働災害医療及び現金給付に関する請求及び決定手続は、アクセス可能かつ透明性があることを確保するよう奨励する。委員会は、災害または疾病の職業的起因に関する調査は、合理的な時間枠内に実施され、給付へのアクセスが不当に遅延しないよう確保する必要性を強調する。
553. [前略]個人の権利の有効な行使及び適正な手続の確保するうえでの、苦情及び不服申立メカニズムの重要な役割を想起して、委員会は加盟国に対して、国外に居住する外国人労働者とその扶養家族に対するものも含め、それらの手続が公正、アクセス可能、手頃な費用で利用可能、透明性があり、迅速であることを確保し続けるよう奨励する。
554. [前略]委員会は、予防措置が労働災害率の削減、保険機関の財政負担の軽減、及び労働災害給付制度の持続可能性の強化に大きく寄与することを強調する。委員会は加盟国に対して、第121号条約第26条(1)(a)及び労働安全衛生に関する関連文書にしたがって、労働関連災害及び職業病を防止するための努力を追求するよう奨励する。
555. [前略]委員会は加盟国に対して、第121号条約第26条(1)(b)(c)に沿って、障害を有するある人々が、適切な雇用を確保、維持及び進展できるようにするために、職業リハビリテーション及び雇用サービスを提供するよう奨励する。委員会はさらに加盟国に対して、第102号条約第35条に沿って、労働災害給付及び職業リハビリテーションサービスの提供の効果的な調整を確保するよう奨励する。
556. [前略]委員会はそれゆえ、労働災害保護に関する最新の文書として第121号及び/または第102号(第4部)条約の批准を促進するために、SRM TWGの勧告を承認した第346回会合(2022年10~11月)における理事会の理事会の決定に注意を喚起する。委員会は、これに関して加盟国は、とりわけ第102号条約の批准キャンペーンの枠組み内で、ILOの技術的支援を利用できることを想起する。委員会はさらに、一般調査における様々な事例によって示されるように、多くの加盟国の国の法令及び慣行が第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約の規定にしたがっている事実を強調する。
557. [前略]この一般調査で取り上げられている条約及び勧告は、ILO内において確立された価値及び原則の融合を反映している。これには、ディーセントな労働、尊厳、平等、及び労働における基本的原則及び権利に含められた最新の要素としての安全と健康の承認が含まれている。
※https://www.ilo.org/resource/conference-paper/achieving-comprehensive-employment-injury-protection
第1章 労働災害保護の目標、目的及び主要な特徴
1.1. ILOの労働災害保護に対する規制アプローチの進化
30. 労働災害保護は、おそらく社会保障のもっとも古い分野のひとつであり、1世紀以上前に多くの工業国で導入された。労働災害は、ILOの社会保障基準が最初に扱ったリスクのひとつだった。時が経つにつれ、労働災害保護の目的、原則及び概念は、人口動態的、経済的及び社会的変化の結果として変化してきた。この進化するアプローチは、ILOの社会保障基準の3つの世代に反映されている。
31. 労働災害に関するILOの第1世代の社会保障基準は、1921年から1934年にかけて採択され、被災労働者及び死亡労働者の扶養家族の補償を受ける資格を認めた。それらの基準は、しばしば使用者または災害保険機関によって直接提供される、現金給付と医療援助を指すのに、「労働者補償」または「補償」という用語を使用している。初期の基準は、使用者の責任メカニズムを認める一方で、使用者または保険者の側が支払不能となった場合であっても補償が継続されることを確保するための適切なセーフガードを確立する必要性を認識していた。
32. 職業リスクの概念は、第1世代の基準が採用されて以来、労働災害保護の主要な要素のひとつである。この概念は、労働災害が職業に内在するリスクから生じること、補償費用は少なくとも設備の修理費用、施設の維持管理費用、または賃金と同じやり方で扱われるべきであることを認める。したがって、労働者または使用者に過失があるかどうかにかかわりなく、定められた規模に従った法律によって決定される量で、補償が与えられるべきである。この無過失原則は、当初多くの国で主流だった不法行為責任アプローチとは異なる。不法行為責任のもとでは、労働者は通常、持続した傷害が使用者の側の過失行動に起因することを立証できた場合にしか、補償を受けることができなかった。使用者の過失を立証する困難さ、及び、労働者と使用者の双方にとって補償の支給及びその額に関する予測可能性の欠如のために、職業リスクの概念が使用者の側の不法行為責任に徐々に置き換わっていった。
33. ILOの社会保障基準の第2世代、とりわけ1944年所得保障勧告(第67号)、1944年医的保護勧告(第69号)、及び1952年社会保障(最低基準)条約(第102号)は、労働災害を含め様々な社会的事故を単一の社会保障制度に統合した。第2世代基準の革新性は、個人にとって必要な生涯にわたる保護に対する体系的なアプローチ、及びそのような保護を保証するための包括的かつ調整されたシステムの促進にある。第1世代基準とは異なり、第102号条約は、傷害の種類によって保護を区別せず、また、労働者一般をカバーする。
34. 第102号条約は、参加型管理に関する基本原則、並びに給付の適切な提供及び機関・サービスの適正な管理に関する国の総合的責任を確立している。第102号条約第Ⅵ部条は、医療の必要性、一時的または初期労働不能、永久的な完全または一部労働不能若しくは機能の喪失、及び労働者の死亡に起因する支援の喪失など、労働災害から生じ得る様々な事故について定めている。さらに、医療及び関連ケア、一時的または初期労働不能の場合の現金給付、障害給付並びに遺族給付を含め、対応する労働災害給付の広範な範囲を定めている。支給期間、給付の水準及び種類、並びに資格要件など、それらの給付に関する定量的及び定性的基準を確立している。第1世代条約とは対照的に、第102号条約は、現金給付の水準及びその決定方法を明示的に確立している。第102号条約はさらに、労働災害給付を含め社会保障給付の費用及びそれらの給付の管理費用は、保険料または税金若しくはその双方のやり方で集合的に負担されるべきであると定めている。したがって、使用者に直接補償を提供することを求めることは、第102号条約を適用する適切な方法とは考えられていない。
35. 労働災害に関するILOの第3世代の社会保障基準は、1964年労働災害給付条約(第121号)[付表1980年改正]及びその付随する勧告(第121号)からなる。第102号条約が社会保障給付の最低基準を確立しているのに対して、第121号条約及びその勧告は、対象労働者人口の拡大、給付率の増加、及び追加給付の提供によって、労働災害に対する保護の水準を引き上げる先進的な基準を定めている。同時に、第121号条約及びその勧告は、第102号条約で確立された財政及び管理の原則に従っている。さらに、第121号条約は、労働災害保護に対する統合的なアプローチの重要性を認識して、現金給付及び医療給付だけでなく、労働関連災害及び職業病を防止するための措置、障害を有する者を労働市場及び社会に再統合するためのリハビリテーションサービスをカバーしている。
36. 第12号、第102号(第Ⅳ部)及び第121号条約の立場が、労働災害保護に対する現代的なアプローチを反映した最新の文書であることが、基準見直しメカニズム三者作業部会(SRM TWG)の勧告に基づき理事会によって確認された。2022年の労働災害文書に関するSRM TWGの第7回会合を受けて、理事会は、第1世代基準の廃止、とりわけ、1925年労働者補償(災害)条約(第17号)、 1925年労働者補償(職業病)条約(第18号)、及び1934年労働者補償(職業病)条約(改正)(第42号)、並びに、1925年労働者補償(最少限度の規模)勧告(第22号)、 1925年労働者補償(裁判)勧告(第23号)、及び1925年労働者補償(職業病)勧告(第24号)の撤回、に関して、第121回総会(2033年)の議題のひとつに設定することを決定した。したがって、ILOとその三者構成員は、第12号条約で求められている農業労働者への適用を含むめることを視野に入れつつ、第102号(第Ⅳ部)及び/または第121号条約の批准及び効果的な実施を促進するよう奨励された。第19号条約及び第25号勧告に関して委員会は、理事会が、カルティエ作業部会の勧告に基いて、第19号条約及び第25号勧告を「その他の文書」または「暫定的な地位を有する文書」に分類したことを指摘する。それらの条約は、もはや最新のものではないが、一定の側面において依然として関連性がある。
1.2. 労働災害保護制度の概要
37. 第102号(第Ⅵ部)及び第121号条約は、特定の労働災害保護モデルを規定するのではなく、労働関連災害及び職業病の場合に保護を確保するための様々な方法を認めている。それらの条約は、条約の要求事項を満たすために、国の労働災害保護制度が備えなければならない主要な特徴を概述している。
38. 加盟国における労働災害保護制度の多様性を認識しつつ、委員会は、そのような制度は、労働者の強制的な加入、健全な財政基盤及び適切な管理を基盤とし、労働者または使用者の側の過失の有無にかかわらず、包括的な範囲の労働災害給付の提供を確保するものであるべきであることを強調する。委員会は、使用者が労働災害給付を直接提供する責任を負ってはならないことを再確認する。委員会は、労働災害給付を適時に提供し、少なくとも条約第102号(第VI部)及び/または条約第121号で定められた最低限の保護水準を達成することの重要性を強調する。
労働災害保護制度の主要な特徴
39. 労働災害保護制度は、無過失原則に基づいて構築されるべきであり、これにより、労働災害が発生した場合、被災労働者、または死亡した労働者の遺族は、使用者の側のいかなる過失も立証することを要求されない。その結果、被災労働者またはその扶養家族は、労働災害保護制度に基づき、自動的に給付を受ける資格を有する。給付の停止は、限定された場合のみ認められる。この点において、第102号及び第121号条約は、給付の停止の理由を網羅的に定めている。
40. 使用者は、労働災害給付の提供に単独で直接的に責任を負うべきではない。それどころか、財源の共有とリスクの分担は、一方で、労働者の適切な保護を確保し、他方で、使用者責任メカニズムのもとで生じる可能性のある使用者に個別の金銭負担を課すことを回避することによって、企業の持続可能性の促進を確保する。
41. 労働災害保護制度は、労働者に対して強制適用を提供しなければならない。保険機関に強制的に加入される者の範疇は、法律で定められなければならない。加えて、それらの者が労働災害保護制度によって適切にカバーされ、また、現実に保険料が適切に支払われることを確保する措置を講じられるべきである。他の社会保険の分野とは異なり、第102号及び第121号条約は、労働災害給付について任意の従業員保険の選択肢を提供していない。
42. 国は、制度の適切な管理及び労働災害給付の適切な提供に、一般的責任を負わなければならない。制度の形態にかかわりなく、国は労働災害保護制度の適切な機能及び健全な財政基盤を確保しなければならない。この要求事項は、政府が半官半民または民間の性格の機関が労働災害保護制度を運営する権限を与えた場合にも適用される。公的機関によって規制されていない制度については、保護対象者の代表が当該制度の管理に参加するか、または助言的な役割で関与すべきである。
43. 労働災害保護制度は、以下の事態を含め、事故に対して包括的な範囲の給付を提供しなければならない。(i)負傷または疾病、(ii)負傷または疾病に起因する一時的または初期労働不能及び関連する稼得の停止、(iii)永久的である可能性のある稼得能力の全部または一部喪失、またはこれに相当する機能の喪失、及び(iv)扶養者の死亡に起因する扶養の喪失。労働災害給付はまた、資格要件、給付の水準及び、並びに支給期間に関して、第102号条約第Ⅳ部及び第121号条約で確立された最低要求事項を満たすべきである。さらに、労働災害給付を受ける権利を確保するために、いかなる適格期間も課してはならない。
[以下省略]
安全センター情報2025年7月号